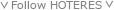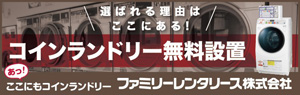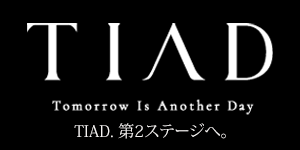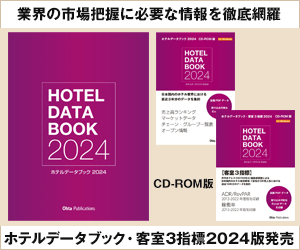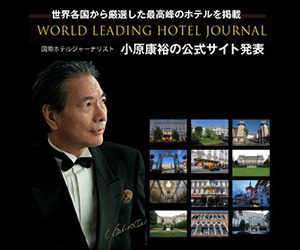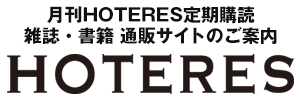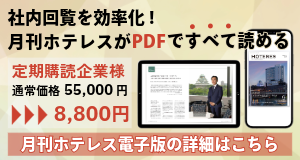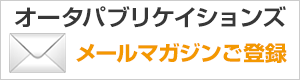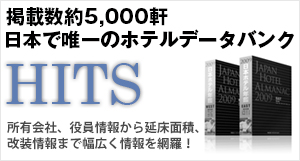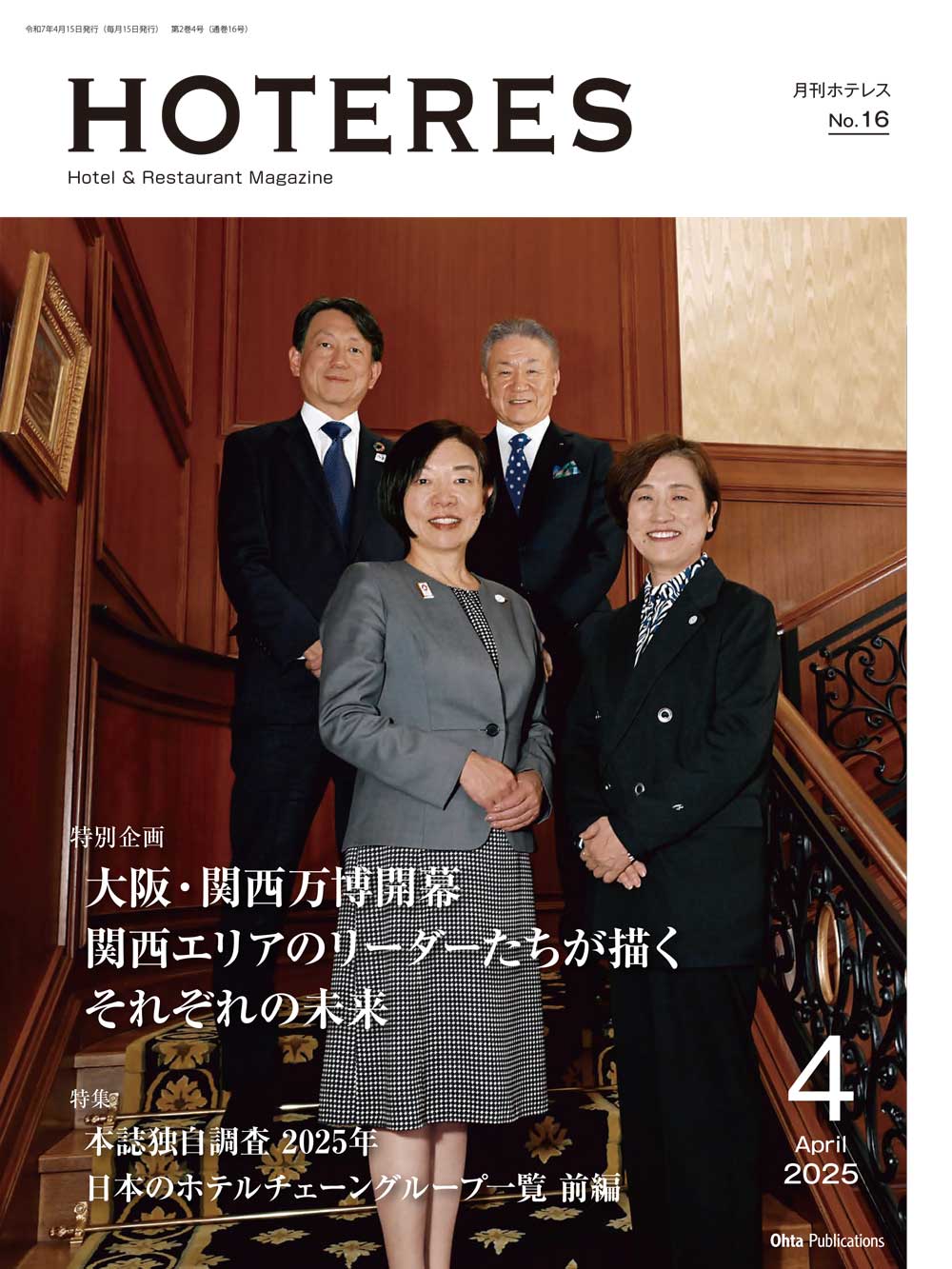セミナーには、50名近いホテルマンが道内各地から参加。現職のRM担当や未来を担う人材など、それぞれの視点からセミナーを受講する
IT ソリューションの提案と導入による企業経営サポートで業界貢献を続ける㈱サイグナスが、JR タワーホテル日航札幌で4 月17 日、自社主催の「レベニューマネジメントセミナー」を行なった。さまざまな条件下で高稼働・高売上にあるホテル・旅館業界が、今考えるべきことはなんなのか。本セミナーを通じて見える業界の今後と、レベニューマネジメントの重要性を、今一度本誌でレポートする。

壇上からの印象的な投げかけで、会場の空気を掴む上垣氏
RM 基礎概念と用語
目的は収益の最大化
2 部構成のセミナーは、前半にレベニューマネジメント(以下、RM)の概要や導入
の目的、後半にサンプルデータを用いた分析例と説明がなされた。
前半壇上に上がったのは、同社 執行役員ASP 事業部長 上垣徹氏。冒頭同氏から会場に向け「ホテルとは一体なんなのか」という質問が投げかけられると、参加者の注目が一気に集まり、良い緊張感の中で講演は始まった。投げかけに対し同氏は「ホテルとは利益を生み出すための企業である」とし、その後本題へと展開。まずはRM の基本原理である「客室販売とコストの関係性」を図で説明し、そこにかかわる固定費と変動費について述べた。続いてRM のプロセスにおけるPlan(=Forecast/ 予測・計画)・Do(=Implement/ 導入・制御)・See(=Analyze/ 評価・解析)と、組織で働く役職とその役割や立ち位置について説明し、役割の明確化と組織全体での理解の必要性を訴えた。稼働率、客室販売単価、RevPARといった基礎的な用語の説明がなされると、最も重要な『売上の最大化』にテーマが移行。モデルケースから理論上の最大売上高について説明し、実際の客室販売価格や期間へ内容が展開され、現場で日々起こっているであろう損失に話がおよぶと「販売機会損失は気づくことができるが、収益損失は見ようとしなければ見えてこない」と述べた。
Demand Forecast(需要予測)のテーマでは、その重要性と戦略的な稼働コントロールによる商品・サービス品質の維持を提唱。Forecast に必要なデータの構成内容を続けて紹介し、365 日の売上とそれらのデータ解析から導き出される自社の売上特性や日別の需要レベルの可視化、また連動する形で、レベル分けによるRateLevel(販売価格)コントロールを、例を挙げながら説明した。その後、収益の最大化と利益率の向上を目的とした戦略的な連泊を述べ、ミレニアルズと呼ばれる新たな顧客世代の存在と価値観について伝えながら「RM は思想であり、方針、文化。すべてのスタッフがビジネスからの利益に集中す
るアプローチや態度であり、思考パターンを切り替え、文化として根付かせることが最
も困難なこと」と締めくくった。
RM の真価を理解する
マーケティングとの融合
休憩をはさんで後半は、同社代表取締役 丸山英実氏による、「RM の応用と活用例」をテーマにした講演が、サンプルデータを用いてなされた。同氏はまずセミナー開催のきっかけについて「周囲の理解不足によりRM 担当者が孤立している状況が見受けられる。経営者のみならず、今までアプローチできていなかった層への訴求により、RM 運用環境の改善を図っていく」とあいさつとともに述べた。
講演が始まると最初のテーマを『分析』とし、三つの要素(比較・構成・変化)を挙げた。そして分析の結果から見る事象と、導きだされる仮説の存在に触れながら「重要なことは仮説をもとにした検証結果から解決策や売上向上のヒントを見つけ出し、具体的戦略を策定すること」とまとめた。また、売上や稼動において自社の過去実績だけではなく、周囲との比較を用い、Plan・Do・See における評価を積極的に行なっていくべきと提言した。『マーケティング』のテーマでは、RM におけるマーケティングの概念に触れ「RMとマーケティングは、需要をコントロールする側と作る側の関係にある」とした上で、具体例を挙げながら互いの役割と情報共有の重要性を説明。バランスの図り方や大切さを述べた。データを用いたパートでは売上とセグメントをテーマに、過去売上から見る販売戦略方針の導き出し方を教示。展開された内容は、予算の作成時期やその正当性にまでおよんだ。
マーケティングの一環である顧客管理についても触れ、RM 的観点から見た顧客の在り方、本来の顧客管理と会員組織の意義について言及。会場全体が自社を振り返る機会となった。同氏は最後に「需要をコントロールするRM 機能と需要を作るマーケティング機能との正しい融合が、年間を通しての収益最大化を実現する」と、今後の業界活性化に期待を込めた。

全体を包み込むような口調と明瞭なトーンで、RMの活用と真価について講演を行なう丸山氏