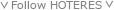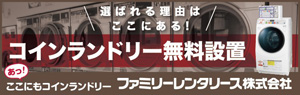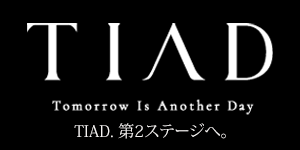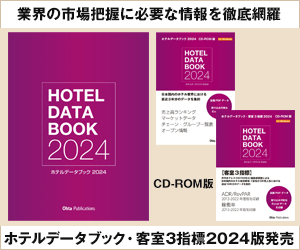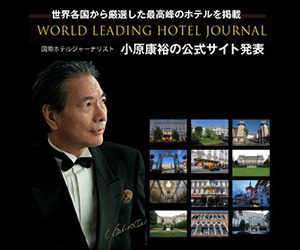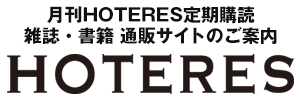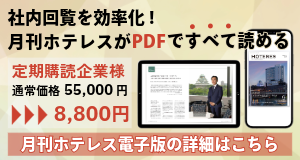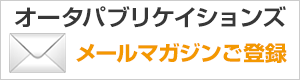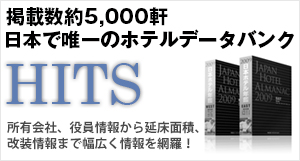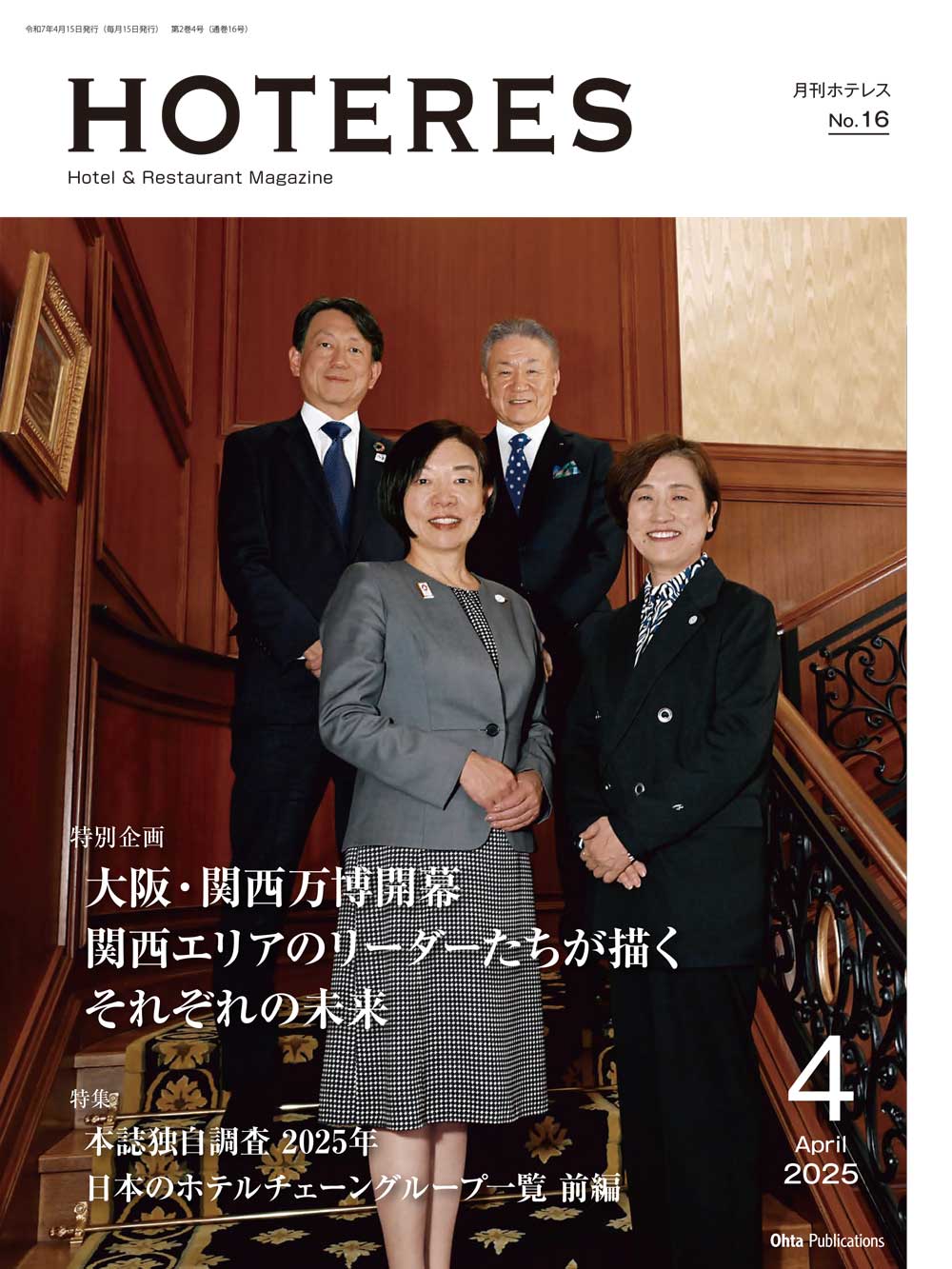東京都の農地面積は減少を続けており、2016 年にはついに7000 ヘクタールを割り込んだと見られている。農業はわれわれの生活を支える根幹である「食」に関わる産業であるが、わが国ではいわゆる「衰退産業」といわざるをえないのが現状である。
しかし、観光を支えるのはその地域の「食」でもある。その意味では、食文化を、そして観光を支える農業の将来について、われわれも無関心ではいられない。
今回の対談相手である小野氏は、田畑の可能性を極限まで追求し、さまざまな楽しみを創造して、国立の谷保という地域における新しいコミュニティづくりに成功している。注目すべきは、なにがしかの計画にもとづいて進めていくのではなく、その都度、その場にあるモノを活用し、必要なコトを実現しうる人間関係の構築に腐心してきたことである。ホスピタリティの根本原理である「不確実性」をむしろ活かして、新しい価値を生み出し続ける秘訣についてうかがった。
農業への想い
徳江 さすがに今日は暑いですね。今は農業に関わっていらっしゃいますが、幼い頃、こんな日は外で遊びまわっていたのでしょうか。
小野 いえ、まったく(笑)…新興住宅地で育ちましたし、あまり自然の中で遊ぶことはなかったですね。むしろ「自然の中で遊びたいけど遊ばせてもらえない子供」でした。でも、虫とか生き物にはとても興味がありましたね。
徳江 そんな幼少期から一転し、いつ頃から自然に親しむようになったのでしょう?
小野 大学で探検部に所属してからです。
徳江 探検部とはまた一気に「自然系」に行きましたね。ある意味、それまでの抑圧が爆発した感じでしょうか(笑)?
小野 それはあるかも…なにせ、アマゾンにまで行ったりしていましたから。
徳江 その後、テレビの制作会社に入るわけですが…
小野 やはり、そういった生き物とか自然とかを扱う仕事がしたかったので、その分野に強い制作会社に入りました。「所さんの目がテン!」の制作で、色々な実験をやらせてもらったりしたのはいい思い出です。