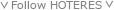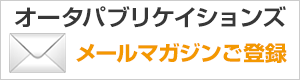本号より、ホテル不動産の開発・投資アドバイザーとして長く活躍し、現在は立教大学において教鞭を執る沢柳知彦氏の経済小説を約6 カ月にわたり集中連載する。普通の駅前ホテルが経営危機から脱するために必要なホテル経営学の知識をちりばめた本作は、ホテルマネジャー職を目指す読者にとって良い学びの機会を提供するだろう。物語は東京・池袋駅西口にそびえる独立系ホテル「ホテルメガロポリス東京」から始まる。
第一回 プロローグ(1)
自動ドアが開き、客とともに師走の冷たい風がホテル館内に入ってくる。朝食・昼食・夕食いずれの時間帯も食事を提供するホテルのレストランをオールデイダイニングレストランと称するが、816の客室数と5つのレストラン、そして大小宴会場を備えたホテルメガロポリス東京のオールディダイニング「ウエストゲート」はホテルのエントランスドアからほど近く、レストラン入口付近では外気が感じられる。レストランマネジャーの花森心平は今の時間帯 - 午後3時頃のアイドルタイムが嫌いだ。館内にはカフェラウンジ「丸池(まるいけ)」もあり、ビジネスマンの商談やご婦人方の集まりは大抵そちらが使われ、「ウエストゲート」は閑散としている。都内外資系ホテルのようなデザートブッフェを絡めたアフタヌーンティーでも出せば人気がでるような気もするが、ここ池袋にそんな上客がいるのか、自信がない。ホテルの売上はここのところ芳しくなく、心なしか館内に活気もない。総支配人の財津浩二の発案で『ホテル活性化委員会』なる部門横断組織が半年くらい前に立ち上がり、花森もそのメンバーとなったのだが、館内全体になんとなく活気がない点は誰もが気にしているようだ。一時期多かった、騒がしいインバウンドグループがめっきり減ったのも理由のひとつかもしれない。目の前に客がいないと漠然とした不安が募る。少しでも活気を取り戻すべく、創業以来大切にしている「家族に接するようなおもてなしの心」を前面に出し、より笑顔で親身な接客をしよう、と委員会で決めたものの、それがどう売上増加につながるのか、よくわからない。それに、まずは接客をする相手がいないとどうにもならない。店内では仲の良い女性ホールスタッフの二人が他愛もないおしゃべりを始めた。普段なら注意するところだが、何しろ客がいない。放っておこう。
「花森さん、何考えてるんですか?」
振り返ると新入社員の森本玲奈が目をくりくりさせながら立っていた。彼女は学生時代からホテルやレストランでアルバイトをし、大学では観光学を専攻し、なるべくしてなったホテルウーマンだ。小柄な体つきにボブヘアが良く似合い、いつも笑顔を絶やさない。所作もキビキビしていて、話をしているだけで元気を与えてくれる。彼女にこそ活性化委員会に入ってもらった方がいいな、と花森はふと考える。まだ、新入社員だけど。
「いや、今日もアイドルタイムの客の入りが少ないなあ、と思って。森本は不安にならない?」
「ランチタイムはそこそこ忙しいじゃないですか。ウエストゲートは喫茶もできるけど、基本的にはレストランなんだからアイドルタイムにお客さんが入らないのは仕方ないんじゃないですか?」
まあ、その通りだ。人気のラーメン店じゃないんだから、ランチタイムを過ぎても客が列をなすなんてことはありえない。そんなこと、新入社員に指摘されてどうする?花森は苦笑いをした。その時、50代と思しき中年男性と30代くらいの女性の二人組が入店してきた。女性の方はスレンダーでスーツとタイトスカートを纏い、セミロングのウェイブをかけた髪が良く似合う。肩で風を切って歩く、いわゆる「できる」キャリアウーマンを絵にかいたような美人だ。歳は同じくらいだろうか。かっこいいな、テレビドラマだったらこんな人と一緒に仕事できるのにな、と花森は思う。この二人、上司と部下?夫婦のようではない。もしかして、不倫関係?余計なことを考える。
「喫茶だけなんだけど、よろしい?」女性客の方が男性客を先導する形で訊いてきた。ちょっとハスキーな声もいい。もちろんですとも、と答えながら、花森は二人を窓際の席に案内する。窓の先には箱庭風の竹林が作られており、都心ながら少しだけ和を感じられるようになっている。何年か前のインバウンドブームの頃には面白がって写真を撮っている外国人もいたが、インバウンド客が減ったこの頃は誰の関心も集めていない。そもそも竹なので季節感もない。今度の活性化委員会で箱庭のイメージチェンジを提案してみようかな、と漠然と考える。
「こちらの席でよろしいでしょうか?」
二人を着席させホールスタッフに引き継ごうと席を離れようとした瞬間、初めて男性客の顔をきちんと見た。知っている。誰だっけ?・・・そうだ、母校・東西大学経済学部の辻田健太郎専任講師だ。卒業がかかった4年生のとき、試験の前日までアルバイトに精を出したのが祟り、先生の指導科目「観光経済論」の単位を落とすことが決定的となった。勇気を出して先生の研究室まで直談判に出かけ、単位取得の約束を取り付けたことを思い出した。意外と気さくに話をしてもらい、同郷の兵庫県出身だということもわかり、予想以上に長く雑談した記憶がある。結局、追試レポートを提出することを条件に単位をくれることになった。おかげで留年せずに卒業することができた。花森は咄嗟に声をかけた。
「辻田先生、私です。15年前、東西大学で単位を落としそうになり、追試レポートで救ってもらった、花森です。」
辻田は驚いて顔を上げ、花森をみた。トレードマークの黒縁丸メガネの視線の奥で、記憶を辿っているようだ。辻田は15年前より年は取っているが、もともと老け顔だったせいか、風貌はあまり変わっていないように見える。
「たくさんの学生を見ておられるのでご記憶にないかもしれませんが、私は同郷の丹波出身で、一度先生の研究室で丹波大納言小豆をどうやって食べるのがおいしいかについてディベートをさせていただきました。おかげ様で無事に卒業し、ご覧の通りホテル業界で働いています。」
「ああ、思い出した。花森くんか。正直、そんなに多くの学生を覚えているわけではないけど、君のことは覚えてる。卒業がかかっていると、切羽詰まった顔で研究室を訪ねてきたよね。確か、ご実家が野菜農家だった?」
「その通りです。覚えていていただいて光栄です。」
「そうか、このホテルで働いているのか。」
そういうと辻田は年季の入ったカバンから名刺入れを出した。差し出された名刺には、立身大学経営学部特任准教授 辻田健太郎、とある。花森の母校東西大学のときは専任講師だったと記憶している。大学の格も上がり、あの頃より出世しているようだ。スーツの着こなしは今一つパリッとしてないが、確か辻田はサラリーマンの経験があるのではなかったか?花森は辻田が講義の合間に語ったサラリーマン時代のエピソードを15年ぶりに思い出した。そうだ、以前は不動産屋だったはずだ。
「僕は今、すぐそこの立身大学にいるんだ。元々僕の専門は経済学ではなくて、経営学でね。ようやくここに経営学を教えるポストが見つかったというわけだ。」
「そうですか。お近くですから、是非ごひいきにしてください。私はここでレストランマネジャーをしています。」
花森も名刺を渡し、今度こそ席を離れようとした。離れ際に改めて女性客の方に目線であいさつをしたのだが、彼女の目は何かを計るように花森に向けられていたことに今更ながら気が付いた。彼女も自分の知り合いだろうか?どこかで接客をしたことがあっただろうか?持ち場に戻りながら考えを巡らせたが、答えはでなかった。
*****
翌年4月1日、花森はホテルの地下1階オフィスにいた。3月末に人事異動が出て、総支配人の財津浩二が新設したポストである経営企画室長に任命されたのだ。室長といっても専用の部屋があるわけではなく、財務部の一角に机があるだけ。部下もおらず、秘書業務は財務部長である近藤誠一の秘書、田辺ひまりが兼務している。これまでのホテル業界人生を通じて接客部門の業務経験しかなく、常に外の天気がわかる窓のある職場だった花森にとって、自然光が届かない地下のオフィスで接客をせずに仕事をするという業務環境の変化は相当なショックだった。しかし、何よりショックだったのは、室長として与えられたミッションだった。人事異動の内示が出た日、財津は花森を総支配人室に呼んだ。花森に年季の入った応接ソファへの着席を進めながら、こう切り出した。
「花森君、今度新しく経営企画室という部署を立ち上げることになってね。君にはその室長をやってもらうことにした。」
財津は50代後半のがっしり系高身長、グレイヘアを短くまとめ、欧米からの宿泊客に挨拶する際に体格•容姿ともに全く引けを取らない。堂々とした振舞い、ゆっくりとした話し方、そしていつも沈着冷静な姿勢は花森の憧れである。そんな財津から何やら重要なポストを与えられることになり、花森の心は踊った。「室長」という肩書も心地よい。何の仕事かはわからないだろうが、田舎の父と母もきっと喜ぶことだろう。だが、財津の顔は暗い。財津の秘書、藤田幸子が無言でコーヒーを二人の前に置き、会釈をして退室したあと、財津は続けた。
「このホテルがここのところ業績不振なのは君も知っているよね。実は3週間ほど前、豊島(とよしま)社長に呼ばれたんだ。社長はこのホテルにこれ以上の金融支援はしないと言ってきた。ここは、彼のホテルなのに・・・」
豊島社長はホテルメガロポリスの社長であると同時に、ホテルの親会社•豊島興産のオーナー社長でもある。豊島興産の本業である不動産デベロッパー業は順調と見え、地元池袋の東口側にビルをいくつも開発し、所有している。ホテルがある西口にはライバル•野座間産業がディスカウントストア•NOZAMAをいくつも構えており、豊島興産にとってこのホテルは池袋西口における勢力拡大の拠点のはずであった。
「財津さん、確かにうちのホテルはここのところ売上不振です。でも、経営環境が厳しいのはうちだけじゃないですよね?活性化委員会を作って改善策をいろいろ話し合っていますし、何より客室稼働率はまだ80%超えを維持しているはずです。親会社の支援はなくても何とかなるんじゃないんですか?」
ホテルによっては総支配人を「総支配人」と呼んだり、英語表記General Managerの頭文字をとって「GM」と呼ぶところもあるが、ホテルメガロポリスでは財津の方針で、誰でも「財津さん」と呼ぶようにしている。財津は目を閉じ、腕を組み、ため息混じりに答えた。
「僕もね、そう思っていた。君も知っての通り、僕はずっと接客部門を歩んできた。正直、数字にはあまり強くない。詳しくは財務の近藤君に聞いて欲しいんだけれど、簡単にいうと、一定の運営利益は出てはいるものの賃料支払負担が大きくて最終的には赤字、ということだ。」
「えっ、賃料負担で赤字って、このホテルは豊島興産が所有しているんじゃなかったんですか?」
「うん。先代の社長が建てた時はそうだったらしいんだけど、90年代のバブル崩壊で豊島興産も一時経営が苦しくなって、2000年代の初めにはホテルの土地と建物を帝国生命に売ったそうだ。それ以来、うちのホテルは帝国生命のテナントとして家賃を払い続けているというわけだ。」
花森も接客は好きだが数字には疎く、とにかく売上を維持していれば経営は何とかなると漠然と考えていたが、どうもそうではないようだ。自分が勤める会社が赤字、と経営陣から聞かされるのはショックである。しかも、本業でそこそこ儲けていても、賃料を払うと赤字らしい。そもそも、「赤字」って、いったいどういう意味なんだろう。会計の勉強をきちんとしておけばよかった。
「花森君、実は問題はそれだけじゃないんだ。豊島興産の金融支援が得られないとなると、活性化委員会で検討している客室改装計画の資金調達ができない。」
「なるほど。だから財津さんは委員会の場で改装計画についてあまり積極的な発言をしておられなかったのですね。でも、銀行からお金を借りてみては如何でしょう?確か、近藤部長はミズナミ銀行出身でしたよね?ミズナミの池袋支店は優良顧客謝恩パーティーを毎年うちで開催してくれています。」
「もちろん、近藤君にも相談している。でもね、ミズナミ銀行との取引関係はこのホテルとしてではなく、豊島興産本体となんだ。豊島興産が保証してくれないとこのホテル単独では改装投資資金の融資は難しいらしい。」
いつもの自信に満ちた表情はどこへやら、財津はいつになく弱々しい話し方をしている。
「そうなんですか。なるほど。経営企画室の役割が見えてきました。このホテルの収益構造を改善し、自力で賃料が払えて改装投資が行なえるようにする、ということですね。ある意味、活性化委員会の役割を正式な部署に衣替えするとも言えそうです。私がどこまでやれるかわかりませんが、ご期待に沿えるよう、頑張ってみます!」
花森にこの難局を乗り越える自信はまったくないが、自分のホテルを救いたいという気持ちはある。活性化委員会のメンバーもサポートしてくれるだろう。総支配人室にのしかかる重苦しい雰囲気を払いのけたくて、花森は敢えて元気な声を上げた。
「花森君、ありがとう。君のその前向きな姿勢には感謝します。でも、問題はそれだけじゃないんだ。」
「えっ、まだあるんですか?」
「うん。実は、これが一番差し迫った問題なんだが・・・。帝国生命との賃貸借契約期間は22年間、再来年の3月に満期を迎える。これまで豊島社長がコロナ禍のときの一時的なものも含めた賃料減額交渉をやってこられたが、これが仇となり、帝国生命はこのままでは契約を更新しないといってきているそうだ。」
「あのぅ、馬鹿な質問をして申し訳ないのですが、契約が更新されないとどうなるのですか?」
「ホテルメガロポリスはこの建物から退去しなければならない。すなわち、このホテルは営業を終了せざるを得ない。」
財津の無感情な言葉が裁判官による判決言い渡しのように部屋に響き、総支配人室はしばし沈黙に支配される。
「あのぅ、ということは、我々は首になり、路頭に迷うと・・・」
「最悪の場合、そうなる。ただ、帝国生命はその後もホテルを継続させようとするだろう。彼らも賃料が欲しいからね。そうなれば別のホテルオペレーターが誘致されることになるけど、ここのホテルスタッフは皆、優秀だ。多くは再雇用される可能性が高いんじゃないかな。」
財津の答えは、わかったような、わからないような答えだ。この部屋に入って来るまでは毎日出社して同じ仲間と一緒に働ける職場がずっとそこにあると信じていたのに、実はあと2年でその職場が崩壊してしまうかもしれない。花森は財津の説明を受け止めきれず、狼狽した。しかし、この部屋が沈黙で支配されるのは怖い。上ずった声を何とか絞り出し、自分の理解を確認する。
「さ、再雇用される可能性があるということは、再雇用されない可能性もあるということですね?」
「そういうことになる。」
目の前のすっかり冷めてしまったコーヒーを一気に飲み干し、財津は一息つく。
「悪い話はここまでだ。花森君、ここからは前向きな話をしよう。帝国生命は当方の継続的な賃料減額要請を撤回し、更に契約更改時に行なう予定の約10億円の大規模修繕工事完了後に7%の賃料増額、すなわち年間16億円の賃料設定に合意するなら契約更新に応じると言っているそうだ。」
「えっ、こちらから賃料減額のお願いをしている状況なのに、帝国生命は増額要請ってことですか?全然前向きな話じゃないんですが・・・」
「そんなことはない。要は活性化委員会で検討している収益改善計画を実行し、ホテルの利益が上がってくれば、客室改装費用も捻出でき、賃貸借契約も更新できる、というわけだ。話はシンプルだろう?」
「ですが、利益を向上させるための客室改装費が捻出できないと改装が行えず、利益が上がりません。」
「花森君の言いたいことはわかる。だから、経営企画室という専門部署を立ち上げ、まずは大規模な改装投資を行なわずに利益を上げる方法を考え、実行に移してもらいたいんだ。利益増加傾向が見えれば改装費用の資金調達も何とかなるだろう。君は入社面接のとき、新入社員時代に勤務先のホテルの業績改善に一役かったことがある、と言っていたじゃないか。是非、その知恵と行動力をこのホテルに貸してくれないか。」
確かに、花森は新卒で入社した地方のホテルで図らずも経営改善の手伝いをしたことがある。ただ、あの時は一切責任をとる必要がなく、経営理論もまったく知らずに行き当りばったりにアイデアを繰り出したところ、たまたまうまくいっただけだ。その後、日々の業務の合間にホテル経営セミナーに出席し、経営コンサルタントの書いた書籍を読み、最低限の経営に関する知識を身に付け、いくつかの転職をし、ようやくこの都心の大型ホテルのマネジャー職にありつくことができた。しかし、これまでは目先の運営をこなすのが精一杯で、自分自身が経営改善計画を立案したり実行したりすることなどなかった。自分に何かできるのだろうか?花森は今更ながら不安になった。入社面接のときはできるだけ良い印象を持ってもらいたくて、新卒ホテル社員時代のエピソードをちょっと盛った気もする。もしかすると財津はあの話を信じて自分を経営企画室長に任命したのかもしれない。これは、まずい。自分だけでは何もできない。ここはまず同僚の知恵を借りるところから始めよう。
「財津さん、お話はよくわかりました。よくわかりましたが、何から手を付けてよいか、よいアイデアがすぐには浮かびません。早速、経営企画室の人を集めて、作戦会議を開きたいと思います。人事異動発令前ですが、よろしいですよね?」
「花森君、申し訳ないが経営企画室は当面、君一人だ。知ってのとおり、うちのホテルはぎりぎりの人数で運営を回している。運営から何人か同時に外すなんて余裕、ないんだよ。わかってくれ。」
「しかし・・・」
「その代わり、各支配人には君に全面的に協力するよう要請するつもりだ。もっとも、このホテルがあと2年の命かもしれないことは当面伏せておく。社内に動揺が走るのは避けたいからね。君の秘書業務は財務の田辺さんが兼務するよう、頼んでおいた。ただ、彼女にも2年の件は内緒だ。」
秘書がつく役職は初めてだ。これはちょっと嬉しい。財務部長秘書兼財務部員の田辺ひまりは30代の中堅社員で、まだ若いのに「財務部の母」と呼ばれ、細かい経理規則を何でも知っていて頼りにされている。ずっと財務畑を歩んできたため、これまで花森との業務上の接点は多くはなかったが、期日の過ぎた経費精算を何度か頼み込んだことがある。意外と柔軟性もあるようだ。彼女なら面倒な管理業務をきっとうまく片付けてくれるだろう。いや、それより、部下もいない状態で利益向上策を検討し実行しなければならないことが問題だ。花森は食い下がる。
「ご配慮ありがとうございます。でも、浅学の私だけでは荷が重過ぎます。どんな若手でもよいので、せめて一人は部下に回していただけませんか?計数の分析とか、書類の整理とか、任せられそうな若手を。」
「わかった。どの支配人も人手を出したがらないんだけれど、何とかしよう。それと、私も少し豊島社長とやりあってね。財務的な支援を打ち切るのは仕方ないとしても、子会社のホテルメガロポリスが倒産でもしたら親会社の信用にも関わる。改装資金は出さないとしても、向こう2年間、最低限の資金繰りの面倒を見てもらうことは約束してもらった。もうひとつ、ホテルコンサルタントを雇用する予算も獲得してきた。」
「予算はどのくらいですか?」
「それが、あのとおり、社長はけちでね。月50万円、1年分。それ以上は出さないそうだ。」
ということは年間6百万円でこのピンチを救ってくれるコンサルタントをみつけなければならない、ということか。高いのか、安いのか、よくわからないが、マネジャークラス一人分の年俸ということは、大したアドバイザーは雇えないだろう。いないよりはましだが、この危機的状況を救ってくれるスーパーコンサルタントの雇用は望めそうもない。
「財津さん、わかりました。与えられた条件の下で最大の結果を出すのが社員の務めです。精一杯がんばらせていただきます。」
そういって最敬礼し総支配人室を後にしたものの、何から手を付けてよいのか、花森には皆目見当もつかなかった。
(次号に続く)
第一回
連載 もてなしだけではもう食えない 立教大学 ビジネスデザイン研究科 特任教授 沢柳 知彦
連載 もてなしだけではもう食えない 第一回 プロローグ(1)
【月刊HOTERES 2020年11月号】
2020年11月09日(月)