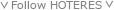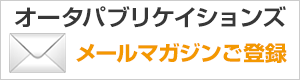Ⅳ.人を動かす(その2)ー 評価について
人のモティベーションを左右する大事な要素に、「評価」という問題があります。
上司や周囲に「評価されている」と感じれば、モティベーションはあがり、より良い仕事をしてその期待に応えようという意識が、さらなる成果を生む好循環につながることが少なくありません。一方で「自分は評価されていない」、「期待されていない」と感じれば、モティベーションは下がり、やる気のない仕事ぶりが悪循環を招くことにもなります。
このように人を「活かしも殺しもする」、また給与や賞与の査定に於いてはまさに「その人の生活がかかっている」、重要な意味を持つ「評価」については、それを行う立場にある人は、その“責任”を十分に認識して、誠実に行わなければなりません。。
「評価」をするうえでのキーワードは、「公平」「公正」だと私は考えています。
元々人の回転、入れ替わりの多い宿泊・サービス業界に於いては、上司が替わるとその部署の人が総入れ替えになるような事例も耳にしますが、そのようなケースのほとんどが、評価が「好き・嫌い」「(相性が)合う・合わない」で決められ、「公平・公正」なものになっていないように思えます。
では評価を「公平・公正」なものにする為にはどうすれば良いのでしょうか。
評価自体人間が行うものですから、感情をまったく排除するのは難しいかもしれません。それでもできるだけ恣意性を排除する為には、「事実を評価する」ことです。
「A君にはこういうところがある」とか「Bさんはいつも…」という、イメージや固定観念は、評価する人の主観に左右されますから、いくら「私はいつもA君、Bさんと接しているからよくわかっている」と言っても、「公平・公正な評価」とは言えません。
日常の仕事の中で、「これは評価の対象となる」と判断した具体的な事実を、その都度記録に残しておくことです。「後でまとめて…」となると、どうしても記憶があいまいになったり、イメージが入り込む余地が生まれてしまいます。

(参考)人事カルテ
「忙しいのに一々…」と思われるかもしれませんが、日付けと概要だけ、Excelのベタ打ちで良いので、気が付いた時に記録に残しておいてください。その都度評価を考える必要はありません。
また、具体的な事実だけを記録するのですから、当然対象は評価をする本人が確認したことに絞られ、「…らしい」といった伝聞や不確かな噂による、誤った評価を排除することができます。
評価を行う際には、こうして書き溜めた事実について、一項目毎に評価を行うことによって、客観的な評価が可能になります。
こうした事実に基づいた客観的な評価は、評価を受けた部下に対してその説明をする上でも大切です。
評価を行った人は、評価を受けた人に対して「説明責任」があります。「なぜ自分はこのような評価をしたのか」について、それを受けた人に対して、きちんと説明して理解してもらうことが、上司と部下の信頼関係を築くうえで重要です。
評価を受けた側に、その評価の理由に対する“納得感”が無いと、評価をした人に対して不信感を持ち、モティベーションは下がることになります。そして“納得感”のある説明をする為には、具体的な事実に基づく評価であることが必要なのです。
評価の説明の際に「君はそもそも…」とか「あなたはいつも…」という抽象的な話をしても、相手は納得してくれません。
「○月○日、あなたがお客様の予約を受けた際に…」というように、具体的に自分のとった行動に対する話であれば、納得感もありますし、「自分のことをよく見てくれている」上司に対する信頼も生まれます。
そして評価を行う本来の目的である「次につなげる」為にも、具体的な事実に基づく評価は重要です。
評価は「しっぱなし」では意味がありません。その評価に基づいて、部下を次のステップに引き上げる“指導”に結び付けることが必要です。
この“指導”の為には、「どこをどうするか」具体的な事例に基づいて、「○月○日のトラブル処理に関しては、あなた自身が代案を出して…」という風に話を進めることが最もわかりやすく、これを抽象的に「トラブル処理にはもっと責任感を持って…」などと話をしても、相手に伝わらない、もしくはその場で聞き流されてしまいます。
部下に信頼される公平公正な評価をする為にも、部下を次のステップに引き上げる指導をする為にも、具体的な事実の記録を是非心掛けて頂きたいと思います。
評価には「絶対評価」と「相対評価」があることは、御存じの方も多いと思います。
運転免許を取る際の学科試験のように、70点(=基準点)以上とれば(何人でも)合格、というのが「絶対評価」であるのに対して、入学試験のように応募者の中から定員数(例えば100人)を選ぶ(この場合90点以上が100人いれば、89点でも不合格となる)のが「相対評価」です。
基本的に企業や組織で人を評価する場合は、各々の人の能力を評価するのですから、「絶対評価」が基本となります。
そして「絶対評価」を行う際に大切なのが、前述の「事実に基づいた個別評価の積み重ね」です。個別の事象の評価から総合点を出すに際しては、個別事象毎の点数を単純平均する方法と、各事象に軽重判断によるウェイト付けをしてから平均する方法があります。
ちょっと考えると後者の方がより正確であるかのように感じられるかもしれませんが、後者は軽重判断の際に評価者の主観が入る余地が大きい為、前者の方がより「公平・公正」な評価になると言えます。
こうして算出した総合点による評価は、できるだけそのまま結論とするべきです。
一旦算出した総合点を、「調整」するケースがありますが、この「調整」に関しては、個人の恣意性が入ることに加えて、相対評価と混同されることが多い為です。
せっかく具体的な個別の事実を評価して、絶対評価を行ったにもかかわらず、最後の点数を見て、「あれ、このB君の点数がAさんより高いのは…」などと考えてしまうケースで、これは絶対評価を行うべきところに相対評価を持ち込んでしまう、評価上の誤り(エラー)です。
ここまでは給料や役職を決める際に必要となる、「能力」を評価することについて述べてきましたが、賞与などを決める際の「成果」の評価についても考えてみたいと思います。
「成果」の評価の方法については、前章に於いて「オーバーブックの損失についての評価」のところで述べたとおり、「加点主義」と「減点主義」の二つの考え方があります。
「加点主義」は、評価の対象となる人が行った仕事の中で、プラスの成果をあげた事柄を評価して点数を積み上げていく評価方法であるのに対して、「減点主義」はマイナスとなったことを評価して持ち点を減らしていく方法、ということになります。
どちらの評価方法を採るかは、各々の組織の考え方によりますが、“新たな事にも積極的にチャレンジして活力ある成長を目指す”一般企業であれば、「加点主義」が合っていると言えます。
これに対して「減点主義」では、例えば“新しい事業を立ち上げて成功したプラスではなく、失敗した場合のマイナスが評価対象になる”のですから、「何もしない方がマシ」という“事なかれ主義”を醸成しがちです。
一般的に「減点評価」をしている典型として言われているのが公務員ですが、現在では実際にはそこまでひどくはない様ですが、一部の「お役所仕事」と言われるやる気のない仕事ぶりが災いして、そのような通説となってしまったようです。
海外を見ても、かつての社会主義国(基本的に労働者は全員“公務員”)が減点主義であるのに対して、資本主義国の発想は加点主義、という色分けで、1990年代にソ連・旧東欧の社会主義諸国が崩壊した結果を見ても、加点主義に優位がある、というのが常識となっているようです。
評価の視点によって、お国柄、社風や企業風土が決まるのですから、いかに評価というものが重要な意味を持つか、がわかります。
では何故社会主義国でもなかった日本の公務員の評価が、減点主義だと思われているのでしょうか。
それは日本人の国民性にも関係しているのではないかと思っています。
日本には「出る釘は打たれる」とか「謙譲の美徳」という言葉があり、人より目立ったり、突出するのを嫌う傾向があります。
これは、日本人が古来より農耕民族として生きてきたことと関わりがあるのではないかと、私は考えています。
人より優れた弓矢や仕掛けを作ったり、人の知らないポイントを熟知するなど、人と違うことをした方がより多くの収穫を得られる狩猟民族に対して、種まきや田植え、草取りや刈り入れまで、人と同じ時期に同じことをしなければ収穫が得られないのが農耕民族だからです。
こうした国民性に根ざしたメンタリティは、サッカーの国際試合を観ているとよくわかります。欧州や南米などの狩猟民族は、高い技量を持ったストライカーが、相手がスキを見せればどんどんシュートを打っていくのに対して、(さすがに最近の若い世代では、「自分」を積極的にアピールする選手も増えてはきましたが…)かつての日本代表はフォワードがゴール前でボールをもらっても、まだ誰か他に“より良い位置に仲間がいないか”を探して、シュートの機会を逸することも多く、歯噛みをした方も多いのではないでしょうか。
欧州や南米の選手が、シュートを蹴って失敗することを恐れずに、ひたすら点を取ることを目指すのは、まさに加点主義の考え方であり、日本人選手が大事な場面で、点を取ることよりも“失敗する(シュートを外す)ことを恐れる”のは、減点主義の意識によるものだと思います。
話しを「評価」に戻すと、「加点主義」の評価に於いては、積極的にチャレンジをした結果、成功した場合にはこれをプラスに評価しますが、その結果が失敗だった、というような場合でもマイナス評価は行わない、というのが基本です。
ただし、「加点主義」と言っても、まったくマイナス評価をしない、ということではありません。チャレンジとは逆に、本来当然やるべきことをせずに失敗したようなケースでは、マイナス評価を行わなければなりません。
もうひとつ、仕事・組織の性質によっては、加点方法に考慮が必要な場合があることも申し添えておきます。
例えば経理や施設管理など、決められた当たり前のことを、漏れなく正確に行うことが求められる部門に於いては、純粋な「加点」を得る機会が少ないことも考えられ、加点方法に一定の配慮が必要な場合もあります。
「成果」の評価に於いては、成果に至るまでの過程にある「努力」や「頑張り」の評価をどう考えるか、という疑問を投げかけられることがよくあります。
これに関してもいろいろな考え方があると思いますが、本来「努力」や「頑張り」は、それが「成果」につながるべきものですから、結果となった「成果」を評価することでそこに包括される、と考えるべきだと思います。
但し、比較的経験年数の少ない若手の人たちについては、残念ながら結果に結びつかなかった「努力」や「頑張り」などを、「取り組み姿勢」として「能力」の方で評価してあげる配慮も必要かと思われます。一方で「成果」に責任のある管理職クラスについては、「結果がすべて」であって、過程の評価は不要であると考えます。
「頑張り」についてよく耳にするのが、「A君はいつも夜遅くまで頑張っている」とか、「B君は休日も返上して働いている」といった評価ですが、果たしてこうした「頑張り」をプラスに評価することは正しいのでしょうか。
この「頑張り」の評価についての誤解は、勤勉を旨とする日本企業特有の「働き」に対する考え方に根差したものだと思われますが、職場に長くいること、仕事に時間をかけることが、「働いている」こと、「評価される」ことにはならない、という点をしっかり理解する必要があります。
同程度の成果を産む仕事を、7時間でできるAさんと、14時間かかるBさんがいる職場で、勤務時間内に仕事を終えて定時に帰るAさんより、毎日遅くまで残業をしているBさんを「BさんはAさんよりも頑張っている」として、高く評価することが正しいか、を考えてみればおのずとその答えはわかります。
無論、余力のあるAさんがBさんの仕事をサポートするか、といった別の観点の評価はあるかと思いますが、ここではこの論議は省略します。
こうして考えると、“残業代”というのが、如何に不合理な制度か、ということがわかると思います。ホテルのフロントや受付のように、お客様が来ようが来るまいが、決められた時間そこに居ることが仕事、というような職種は別にして、一般的には上記のような場合、Aさんには残業代は支払われませんが、Bさんには毎日かなりの残業代が付くことになります。
この場合、残業代は能力の高い人よりも、能力の低い人の方に多くの給与を支払う、という点で、極めて不合理といえ、それ故仕事の中身によって給与が決まる「年棒制」を採用する欧米企業では、純粋な工場労働者など一部の例外を除いて、残業代という考え方はありません。
「評価」については、評価を行うこと自体よりも、その結果を如何に本人に伝え、次につなげるかがより重要である、と「2」で述べた通りですが、その際に優れたところを持つ部下の「良いやり方」を、他の部下にも伝えて、模倣させることによって組織全体のパワーアップにつなげることも、部門責任者の重要な役割です。
例えば、都内のタクシー会社で、普通の運転手さんが1日に平均1~2万円程度の売り上げであるのに、一人だけコンスタントに5~6万円の売り上げをあげる、という人がいる場合、上司としては、この人がどのような行動パターンを取るかを運転日報やGPSで分析して、「朝10時までは郊外に居て人の動かない都心には入らない」「10時以降は都内のオフィス街やショッピング街」「夜は必ず繁華街に戻る」などの“稼げる行動パターン”を、他の運転手さんにも模倣させることが重要で、この運転手さんが持つような“仕事の上で発揮される優れた能力”(=付加価値)をコンピテンシーと呼び、この能力を活かして汎用にした“勝利の方程式”を、コンピテンシーモデルと呼びます。
コンピテンシーモデルを共有化することによって、一人の優秀な運転手さんの他にも、普通よりも稼ぎの多い運転手さんが多く誕生することになり、組織の力は大きく向上します。