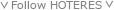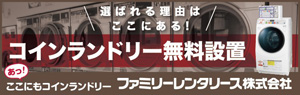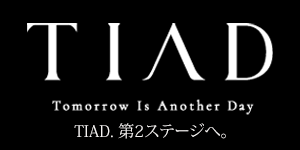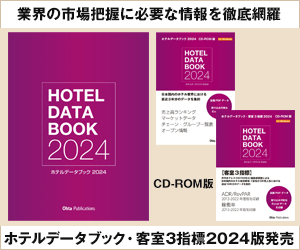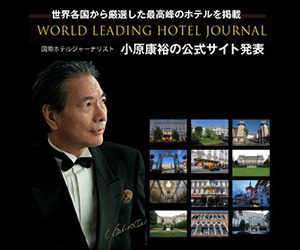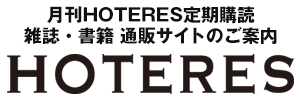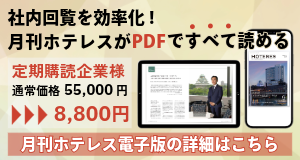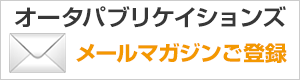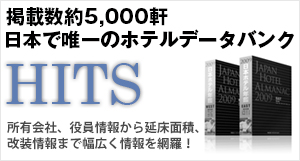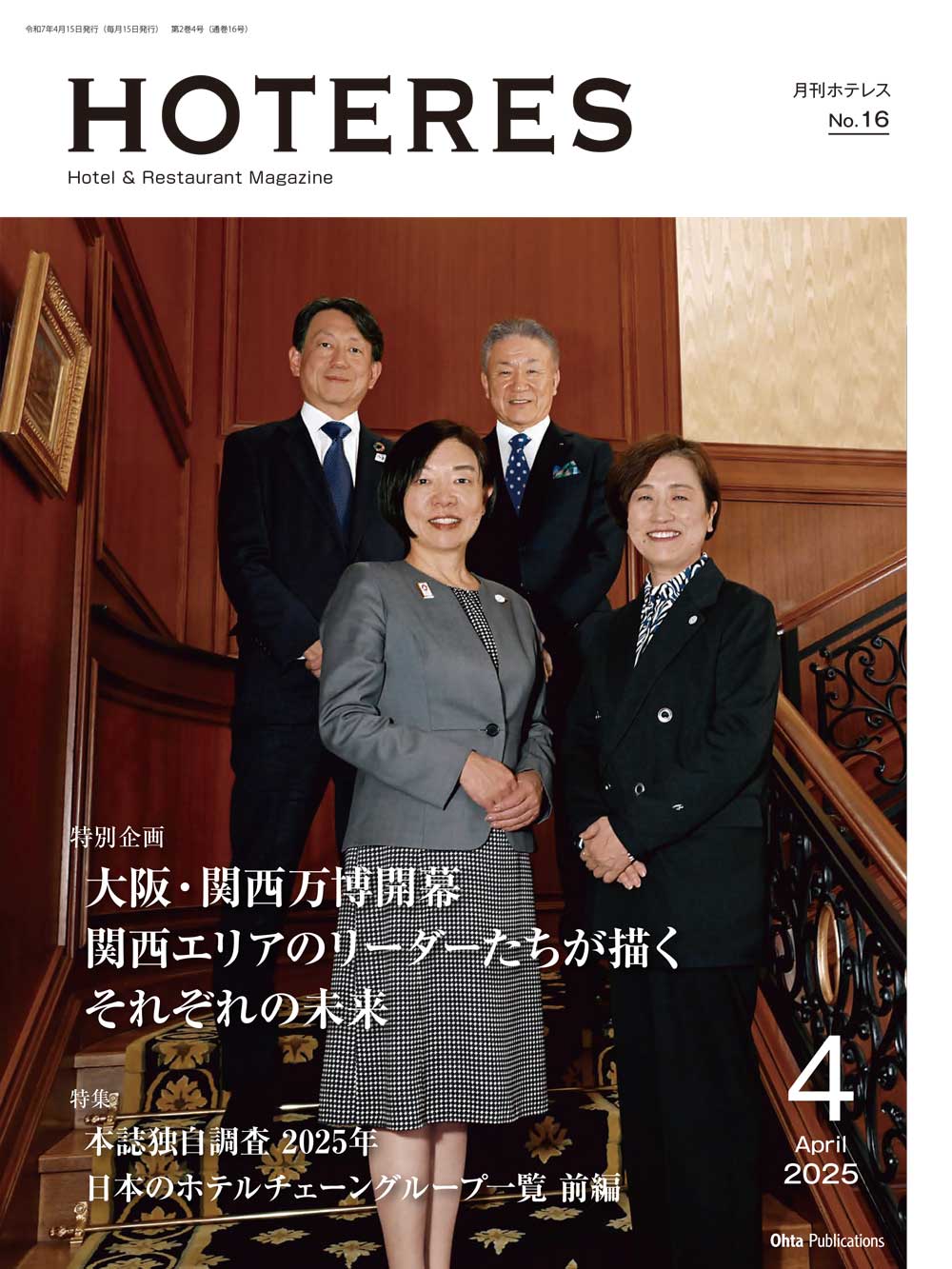日本はドイツ、フランスといった国々と同じ方法を採っていて、法定雇用率を設けることで企業に障害者の雇用を義務づけていますが、義務の対象となる企業はこの法定雇用率に基づき従業員のある一定数障害者を雇用しその報告を行なう、できない場合には納付金の発生や行政指導が行なわれ…といった仕組みになっています。直近ではつい先日、2018 年の4 月から民間企業における法定雇用率が2.2%に引き上げとなったばかりです。
雇用義務の発生は1976 年に身体障害者を対象に始まっていますが、雇用促進法自体がもともとは身体障害者のみを対象に1960 年に制定されており、これは戦争による傷痍軍人の雇用先確保が背景にあったとされています。1997 年には知的障害者についても義務化の対象になっていますが、雇用の義務化とは「〇〇障害の方をどの企業も一人は雇わなければならない」ということではなく、「障害者法定雇用率算定上の統計に加わる」といった意味になります。これによって法定雇用率も引き上げになっていくわけです。精神障害者については2006 年より雇用カウントに加えてもよいということになっていましたが、2018年に精神障害者の雇用が義務化されることによる雇用率の引き上げを見越して、厚生労働省からの発表があった2013 年ころから雇用市況がさらに活発化してきています。
結果、これまで採用実績のあった障害に限らずさまざまな障害のある方の採用を検討する企業が増え、前述の通り精神障害者の雇用が増えてきました。
一人一人が違う存在であること
障害者雇用の推移や現況について書きましたが、日々就労支援の仕事をしていて思うことがあります。“障害者”と一言で表現されはするものの、持っているスキルや特性、困り事などは一人一人異なるということです。もちろん障害の種別によってある程度働く上で発生する障害や一般的な症状などは把握しておくことができますが、特に精神障害、発達障害の方は障害が目に見えて分かりづらく、そうしたことを理由に企業側が雇用に踏み切れないケースもまだまだあるなと感じています。
雇用が進んでいる企業においては外部支援機関との連携を活用し、障害特性についての情報を収集したり、社内の障害者雇用に対する理解を促したり、職場実習の受け入れを行なうなどの取り組みを積極的に行なわれているかと思います。
また、「障害者雇用=義務」といった型にはまった考え方ではなく、自社の事業や風土、文化に合わせて雇用の在り方を考えたり、価値を創出しているところが多いように感じます。
障害や症状にかかわらずもともと人によって得意や苦手はあるものですから、今後の障害者雇用における考え方は「“障害者という存在”に向けて業務を一律に切り出すのではなく、障害のある方一人一人のスキルや特性に合わせて業務を調整する」というところへシフトしていけるといいなと思っていますね。