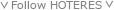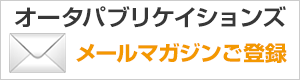看板を背負って仕事をするな
その土地には建設工事用の柵が築かれていた。いずれ建物がせり上がってくるのだろう。だが、内部はまだ歯が抜けたような状態だった。
2013年まで、ホテルがその場所で営業していた。ホテル西洋銀座。日本で初めてのスモール・ラグジュアリー・ホテルといった位置付けで、バトラー・サービスを提供して一時代を築いた。そんなホテルがわずか26年で、呆気なく姿を消したのである。
昨今の業界の激変ぶりをうかがわせるような廃業だったが、片野はそのホテルで勤務したことがあった。職種はそのバトラーである。
執事と訳されるその職種は、滞在客の何から何まで世話をする役目である。顧客のふところに飛び込むようなその仕事に、片野は意気を感じた。
すでに30代の半ばを過ぎた片野は、それなりに経験を積んでいた。だが、これほどの高級ホテルでの勤務は初めてだった。それだけに、長年抱いてきた、自分の思うことでお客さまを満足させたいという長年の夢を叶えてみようと決意したのである。
当時、日本では珍しく、最高度のバトラー・サービスを提供するホテルだけに、さすがに、周囲には有能な人が多かった。ただ、それでも――

かつての西洋銀座のロビー
看板を背負って仕事をするな
昨今の業界の激変ぶりをうかがわせるような廃業だったが、片野はそのホテルで勤務したことがあった。職種はそのバトラーである。
ホテル業界のある協会に所属していたとき、片野は、パリの超一流ホテルであるプラザ・アテネのコンシェルジュの講演を聞く機会があった。その中で、片野は、心に深く刻まれる言葉を耳にした。
「君たちはいま、有名なホテルに在籍し、働いています。しかし、世界には、田舎町の無名のホテルでも有能なコンシェルジュはいます。有能な人は場所を選ばず、どこにいても能力を発揮するものなのです」
……なるほど、大切なのは看板ではない、真の実力なんだ。有名なホテルで働いているからといって、自分を過信してはいけない。勘違いしてはいけないんだ。
日本の社会はどちらかと言えば、看板社会である。ブランドが人の行動を大きく左右する世の中である。
こんなことがあった。片野の知人が日本の超一流ホテルで働いていたとき、その知人の名刺を得ようと、人の列ができたことがあった。しかし、彼がそのホテルを辞めると、彼を訪ねる人はいなくなった。実力があるにもかかわらず、彼を正当に評価した人は皆無に等しかったのだ。
看板に頼ってはいけない、自分は自分のなすべき仕事をしていくことが大切だ、そうすれば実力を蓄えることができるはずだ――片野は自分に言い聞かせた。
*
ホテル西洋銀座の顧客の一人に、アラブの有力者がいた。その人は特に気難しい人だった。
片野は担当の一人として、接遇に当たった。あるとき、同僚が片野に尋ねた。
「片野さん、あの方、お見かけしないけど、どちらにいらっしゃるかご存じですか」
「アメリカに行かれましたよ」
「えっ、本当ですか。ご予定をあまりお話にならない方なのに、よく教えてくださいましたね」
片野は、このホテルの仕事を心底、楽しんだ。楽しんだというと語弊があるかもしれない。言い換えると、ほかのホテルには見られない価値基準で動けるところに魅力を感じて働いたのだ。
例えば、最初にお客さまを客室にご案内し終わったら、即座に所定の部署に戻ってくるのが一般のホテルの常識である。
しかし、このホテルでは、これでは仕事にならない。ウェルカム・ドリンクを提供しながら、あるいは、荷解きをしながら、お客さまの滞在目的を把握し、詳細な日程を聞き取るのが大切だからだ。
「奥様のお買い物のご予定はありますか」
「お嬢様のお誕生日が明日と伺っております。お祝いをどうなさるか、お考えがありますでしょうか」
「美術館巡りをなさりたいということでしたので、おもな展覧会の資料を集めておきました。お勧めは……」
このような問いかけや提案、情報収集を行なうのである。30分程度かかることも珍しくはない。先のアラブの有力者の一件も、このような会話の中で、片野が「マイ・フレンド」と呼ばれるほどの親近感を得ることで、入手できた情報だったのだ。
そして、こうしたサービスは、片野が前々から考えていた理想であった。
……自分が思っていたことは間違いじゃなかったんだ。
*
実は、片野氏はもう一つ、印象に残る言葉をお客さまから得ている。その後に勤める伊勢志摩のリゾートホテルで、顧客から「あなたがいると、何だか空気が変わるね。柔らかく感じるよ」と言われたのだ。
一生懸命仕事に努めれば、それはお客様に伝わるものなのだと悟り、片野は自信を深めた。
後に、片野はビジネスホテル、あるいはバジェット・タイプと呼ばれるホテルの経営に携わることになるが、こうした経験から、「お客さまにして差し上げられることはでき得る限り提供するように」とスタッフに教えるのだった。

英会話の教本を丸暗記すればいいじゃないか
誰もがはじめから仕事ができるわけではない。片野もそうだった。
片野が最初に入社したのは、まさにこれから開業しようとするホテルだった。ただし、入社時には正式に開業していなかったため、新人研修は別のホテルで受けた。そのホテルでも社員のような扱いを受け、自分は恵まれている、幸先のいいスタートが切れそうだと思った。だが、明るい展望は間もなく打ち砕かれた。
そのホテルのロビーに初めて出たときのことである。ベテランの先輩がつかつかと寄ってきて、こう言ったのだ。
「片野君、お客さまにお名前を尋ねるとき、英語でなんて言うんだっけ?」
突然の質問に、言葉が出なかった。
「えーと、What’s your name?ですか」
「馬鹿! May I have your name,please?だろ。これまで何を勉強してきたんだ!」
片野は冷水を浴びせられた気分だった。……そうか、そうだよな、分かっているようで、分かっていなかったんだ。
前途洋々に思えた気分が急速にしぼんでいくのを感じた。
しかも、悪いことに、正式に入社した新規ホテルでは、最初にお客さまに接するベルボーイを務めることになり、なお悪いことに、頼りになる先輩がいなかった。周囲にいるのは専門学校の卒業生ばかりで、逆に質問されて冷汗をかくこともしばしばだった。
片野は、事あるごとに矢面に立たされた。
ともかく最低限の英語を身につけないと、話にならなかった。片野は一計を案じ、1冊の本を手に取った。ホテルニューオータニが発行していた『ホテルの実務英会話』である。
さて、これをどうするか。考えた挙句、理屈抜きで、丸暗記した。
幸い、ホテルの玄関回りやフロントで交わされる英会話は、定型句が多い。一句一句覚え、使いこなしていけば、何とかなるのではないか。場数を踏めば、舌の動きも滑らかになるはずだ。「習うより、慣れろ」だ。
その割り切り方が功を奏した。数年後、アメリカに本社を置くチェーン・ホテルでフロントに立ったとき、同僚が帰国子女ばかりの中で、そのホテルの関係者から「片野さん、英語、うまいですね」との褒め言葉まで頂戴するようになった。
「冗談はよしてくださいよ、決まり文句を話しているだけなんですから」
と言って、片野は照れた。
その片野が、前述したように、ホテル西洋銀座でアラブの有力者と親密な関係を築くことになるのである。

- Rホテルズインターナショナル
- 片野 真治 プロフィール