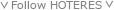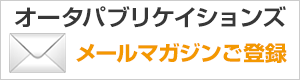欠けた部分に金継ぎを施した器。使い込むほどに 味が出てくる
「和食」への熱い思いが結実した“予約の取れない店”
東京の渋谷から恵比寿に向かって明治通りを歩いていくと、ほぼ中間点にある並木橋交差点。渋谷川に沿った両脇に丘を抱え、右に登れば代官山、左へ登れば緑豊かな金王神社へと続く、散歩好きには有名だが、それぞれの駅から距離があり、必ずしも交通至便とは言い難いこの場所に「並木橋なかむら」はある。
この地を選んだ理由について同店を運営する( 有) フェアグランドの代表、中村悌二氏は次のように語る。「渋谷の商業が南下し、恵比寿の商業が北上して、それがミックスしてこれからさらに変化・発展していく注目のエリアだと思っていますし、このお店以外にもさらにこのエリアでやってみたいと思っています」
同氏が代表を務めるフェアグランドでは現在「並木橋なかむら」を含め7 店舗を運営している。「最初に下北沢にバーをオープンしてから今年で23 年目になります。たくさんの店を経営するというより、一店一店丁寧な店づくりで、地域や街に愛される店を作りたいと強く思ってこれまでやってきました。その中でも、自分の名前を冠したこの店は、本店と言える存在です」と中村氏。
カウンターを中心にフルオープンキッチンとなっている店内は、活気にあふれ、ほぼ100%予約で埋まっているそうで「一度来てくれたお客さまにまた来ていただけるように、毎月定番ものを除きメニューを変更しています。その他お勧めとして、毎日刺し身から季節の野菜と10 ~ 15 品くらいをご用意しています」と徹底したリピーター化への取り組みもあり、予約が取れない店として有名だ。
「と言っても、堅苦しい雰囲気の店ではなく、コロッケから最高級のあわびまで、みんなでシェアして、気取らず和食の魅力を堪能してもらえるとうれしいです」と中村氏は微笑む。
そんな中村氏が「和食」の店についてこだわっているのは、静と動の対比の演出だという。「和食=静、例えば懐石料亭で静かにいただくというのではなく、静と動の演出を施すことによって、そこにストーリーが生まれます。そして、その対比の美しさに人は感動すると考えています」と中村氏。
大通りから細い脇道に入ったビルの2階にひっそりとたたずむ同店には派手な看板はない。しかし、その玄関をくぐった瞬間、『いらっしゃいませ!』の声とともにはじけんばかりの活気と熱気ある店内に遭遇する。そして、その勢いに驚いたのもつかの間、個室へと案内されると再び静寂の時間が訪れる。同店ではこうした押し引きの演出が、サービスだけでなく、料理や器など至る所にあふれている。
器から始まるストーリーが差別化へとつながる
和食では、刺し身や和え物、揚げ物や汁物など、洋食よりも多くの種類の料理が供される。それに合わせてその都度変わるのが器であり、料理の演出には欠かせないものだ。その器について中村氏に尋ねたところ「料理のメニューと同じく、器に関しても常に同じものが被らないように配慮しています。うちの店で言えば滞留時間の2 時間から2 時間半の間、料理と同じように器も一緒にお客さまと時間軸を共有するわけですから、本当に重要なパートナーだと考えています」と答える。「もっと言えば、この器にこの料理を盛り付けたいとか、メニュー開発にもつながるし、あるいは雰囲気に合った内装デザインは? とかサービスは? みたいな広がりも出てくると思います。例えて言うなら、料理やサービスがお店づくりにおける主軸打者なら、器はさしずめ2 番打者という役割でしょうか。控えめだけどとても重要な役割を担っているということです」と中村氏は器に対するイメージを語る。
「残念ながらどんなにいい器を使っても器は割れるものです。でもいい器を使うことによって、手に触れそのぬくもりなどを感じることによってその価値を学び、それによって器の扱い方が変わり、スタッフの動きが変わる。結果として、いい物はなかなか壊れなくなる」
同店では、それでも欠けたり割れたりした器には、金継ぎを施して使っているという。「手に持って使うものなので質感の違いが価値の違いを生む。同じ器にも違いが生まれる。料理やサービスと同様、手間をかけることによってそこにストーリーが生まれ、感動を呼ぶ。その積み重ねが重要だと考えています」
決して現状に甘んじることなく常に新しいストーリーを探している中村氏。次に狙っているのは、「並木橋なかむら」から想像できるものではない規格外の物をお客さまに提供することだそうだ。

「並木橋なかむら」オーナー、㈲フェアグランド 代表 中村悌二氏