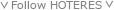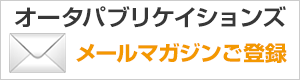まだ土と苗だけのブドウ畑。この一帯で1 ㏊の面積があり、一人で管理する限界は2 ㏊と言われているが、畑づくりと収穫はまた別の話だ
ワイン造りは農業だ
ワイン関連の現地視察や見学といえば、ブドウ畑や醸造設備の見学というイメージがあるが、すべての基となる畑づくりはそうある機会ではない。長野県長ながわまち和町でワイン造りをスタートした㈱アルテレゴ(中嶋卓也代表)は4 月下旬から5 月上旬にかけて、現地でのブドウ畑造成に向けた苗の植え付け作業のボランディアを募集した。中嶋氏のブドウづくりは、長和町の地方創生事業の一つ「黒曜(こくよう)ワインぶどうプロジェクト」の一員としてスタートしたもの。2016 年5 月に研修生として採用された中嶋氏は昨年まで東京・神楽坂でワインバー「トランブルー」を経営しながら、日本ワイン農業研究所「アルカンヴィーニュ」が開講している「千曲川ワインアカデミー」や現地農家などで農業や醸造に関する教育・トレーニングを受けてきた。このスタートアップは本誌別冊『進化するビバレッジ「酒のSP」2016』でも紹介している。ワインバーは昨年末で閉店し、現在はワイン造りの根底であるブドウ栽培のスタートに専念している。


農業への参入障壁と耕作放棄地
中嶋氏や関係者による、農業への参入障壁の説明はわかりやすい。自家菜園ではない事業としての農業をスタートさせるには、農地を持っていることが前提条件だという。一方で、農業用地は農家でなければ取得できない。この堂々巡りを解決するために、研修修了者への農業就業を同プロジェクトがサポートしている。
一方で、今日の日本は耕作放棄地だらけだ。農林水産省によれば、耕作の放棄 により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能とされる「荒廃農地」は2014 年で27 万6000 ㏊におよび、抜根や整地、区画整理などで再生が見込める土地はおよそ半分の13 万2000 ㏊、また主観ベースでの耕作放棄地、これまで耕作していた土地で、過去1年以上作付けせず、この数年の間に再び作付けする意思のない土地は2015 年で42 万3000 ㏊にわたる。さらに中嶋氏によると、こうした土地が相続未登記となっているケースは少なくない。二世代、三世代前の名義のまま農地が放棄されている場合、孫やひ孫など数十人がその利害関係者となり複雑化する場合も少なくないようだ。こうした状況下で中嶋氏は、長和町和田宿エリアの土地2 ㏊を確保。本当の意味での“ ヴィニュロンへの道” をスタートさせた。


苗木不足は自作で
3000 本をこの春に植え付け
さらに、今日の日本ワインの課題は苗木不足だ。特に甲州など人気の高い国産品種の苗木確保は困難と言われている。そこで中嶋氏は、接ぎ木によって苗木を自作した。品種はシャルドネ、ピノ・ノワール、メルローやカベルネ・フラン、シュナン・ブランなど複数種あり、この日はピノ・ノワールの植え付けに参加した。
よく見かけるブドウ畑のような畝ごとに一直線であり、等間隔に整然と並ぶ植え付けが理想だが、現実は異なる。まっすぐ植えるのもひと苦労だ。苗を植え、粒の細かい土からを根や株の周辺に隙間を作らないようにかけていく。水をひとかけして土の密着度を高め、さらに土で埋めていく。その上から踏み固め、仕上げにもうひと盛りすれば良いのだが、この作業一つの重みは原稿の数行とは異なる。この1 本にワイン1 本、生産者の生活が懸かっていると思うと手を抜くことはできない。土と苗に向き合う真剣勝負だから、畝一列を植えるだけでも結構な時間を要する。畝の両端への杭打ちやワイヤーを引く作業なども、見ているだけでその苦労が伝わってくる。
この日に植え付けができたのはおよそ100 本強。5 月中に完了させる予定の3000 本から収穫できるのは20 年の秋になり、醸造、瓶詰をしてワインとなるのは21 年という気の長い道のりだ。
「酒づくりは農業だ」とはよく聞く言葉だが、生産者との接点はそれを率直に伝えてくれる。そして小規模であるほどに、瞬間的な人手が必要な時がある。美しい畑を見るのも良いが、その原点となるフィールドを造ったり、“ 本気の収穫” に参加する機会に接するのは、酒類や飲料、食品の何よりの理解につながるだろう。スタッフ研修の一環としてもお勧めしたい。