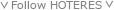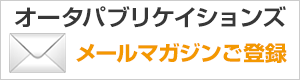名ホテリエには、それぞれ独自の流儀で「おもてなし度」を高めた。ある人は握手で、またある人は現場を隅々見回ることでスタッフの志気を高め、顧客とのコミュニケーションを深めていった。
戦勝国の元帥もただの宿泊客
今年は戦後70周年である。1945(4 昭和20)年8 月30 日、厚木飛行場に降り立った連合国軍総司令部のダグラス・マッカーサー元帥は、日本統治の最初の数日間をホテルニューグランドで過ごした。かつてハネムーンでも滞在したホテルだ。出迎えたのは同ホテルの会長・野村洋三である。彼は威厳を保った姿勢で、次のように接したという。
「失礼ながら、自分は支配人ではない。ここの持主である。よくおいで下さった。当ホテルの主として謹んで貴方に敬意を表する。お泊りになられる間は、出来るだけのサービスを尽すつもりでいるから、なんなりと言付けていただきたい(以下略)」(『文藝春秋』1956 年8 月号)。
この野村の言動からは、敗戦国側の卑屈な態度はまるで感じられず、
「いま思うと、随分滅茶なそして思いきった挨拶をしたものだと、われながら失笑を禁じ得ない」と記しているが、「元帥といえども私の眼から見れば、飽迄までもただの宿泊人と変りはなかったのである」と、当時の心情を吐露している。
戦勝国側の統治者に対して、全く恐れを抱かずに、野村はホテリエの職務に徹したのである。いわば敗者が勝者をもてなすという接遇における究極の構図になるのだが、野村の英語はどうだったのか。後の会長・原範行氏によると、「発音は日本式な感じですが、しっかりした英語を話される。マッカーサーはそういう方に対するリスペクトは非常にしたと思うんです」(有隣堂発行『有鄰』478 号、2007 年)ということだった。それにしても、野村はなぜ、このような姿勢を貫くことができたのだろうか。