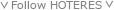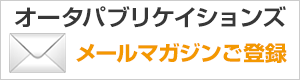2023年10月18日(水)ザ・リッツ・カールトン東京「タワーズ」にて、フランス国家最優秀職人章「M.O.F.」受章のシャリュキトリシェフであるセバスチャン・ゾザヤ氏と、ローヌ地方を代表するワイナリーである「M.シャプティエ」のミシェル・シャプティエ氏を招いた一夜限りのコラボレーションディナーが開催された。
【当日のメニュー】
Amuse bouche
ヴォライユ3種のパテ・アン・クルート リンゴとビーツのジェル バスク風シードル
豚の頭のスナッケ タコ足 ピペラードソース
パリジェンヌ風ブーダンノワール ジャガイモとエスプレットのサイフォン
豚肉のパイ包み 酸味のある赤キャベツのジュ しゃきしゃき野菜
我が家のガトーバスク
【ペアリングのワイン】
‘Esteban’ Vin de France Brut Nature Bio NV
CrozesHermitage Blanc Les Meysonniers 2020
Hermitage Blanc Chante Alouette 2018
Cote-Rotie La Mordoree 1997
Ermitage Rouge Le Pavillon 2006
Ermitage Blanc Le Meal 2009
La Clairette de Die Methode Ancestrale Bio NV
【貴重なコラボレーション】

セバスチャン・ゾザヤ (Sébastien Zozaya)氏
セバスチャン・ゾザヤ (Sébastien Zozaya)氏は、2019年にMeilleur Ouvrier de France Charcutier Traiteur(シャルキュティエ&ケータリング部門 国家最優秀職人章)の称号を得たシェフだ。フランスの伝統を尊重し、新たな規範を生み出すことで、シャルキュトリの現代的ビジョンを提案している。

ミシェル・シャプティエ(Michel Chapoutier)氏
ミシェル・シャプティエ(Michel Chapoutier)氏は言わずと知れたローヌ地方を代表する造り手で、一貫した家族経営のもと7代に渡り畑を守りながらテロワールを尊重し続けている。早くからビオディナミ農法にも取り組んでおり、伝統を重んじながら現代の要請にも真摯に応えるオーセンティックで先見性のあるワインを生みだしている。
なぜこの二方のコラボレーションが日本で行われたのかと言うと、前日の10月17日に「第8回パテ・クルート世界選手権アジア大会2023」決勝の審査委として来日していたからだ。シャプティエ氏と25年に渡って交流のあるサンドロ・ガンバ氏がザ・リッツ・カールトン東京総料理長を務めることもあり、今回奇跡のようなコラボレーションが東京で開催されることとなった。この大変貴重な機会にザ・リッツ・カールトン東京よりお声がけを頂いたので、レポートしていきたい。
【シャルキュトリとは何か】
シャルキュトリと言っても扱う幅はとても広く、ハム、ソーセージといった現代日本の食品小売店でも目にするものから、パテやテリーヌといった飲食店の定番メニューのものまである。フランスの歴史の中で「シャルキュトリ」を紐解いていくと、フランスの食文化が育まれる中、様々なギルドが専門性をもって発達していた様子が伺える。例えば下記の一文だ。
「シェルキュイティエ※は、豚やその他の肉をパテ、ソーセージ、ハムなどの加工品にして売れるが、豚を食肉解体する権利はない」
ジャン=ピエール・プーラン, エドモン・ネランク『フランス料理の歴史』(山内秀文訳)P.107より
※シェルキュイティエは原文ママ
「chair(肉)にcuite(火を入れる)」が語源と言われているが、保存性を高める方法は火入れのみに限らず、浸漬によりタンパク質を変質させる方法や乾燥によって水分活性を押さえる方法などもある。様々な素材に対して塩漬けや乾燥、発酵や熟成、燻製などの製法を組み合わせていけば、多種多様な食肉加工品を手掛けることが可能になる。
以前、フランスを仕事で訪れた際にアンデュイエットを食べたことがある。独特の香りを持つアンデュイエットを食べてフランス料理の一端を知れた気がした。今回は「M.O.F.」受章のシャリュキトリシェフの品ということで、新しい経験ができることに胸が躍った。

実際、ゾザヤ氏のリエットを頂いた時に自身の中で「シャルキュトリとは何か」の一筋の見方が生まれた。それは、組織をどう使うのかということだ。
俗に肉と指される可食部は筋肉(骨格筋)が主体であり、骨格筋は筋線維が束になってできている。そして、形態特性の違いから赤身と白身という具合に、色としても分類が可能となる。遅筋性のものはミオグロビンが多いため赤くなるし、収縮のエネルギーとなるアデノシン三リン酸(ATP)やアミノ酸量という視点からも赤身と白身の違いが見えてくる。
ゾザヤ氏のリエットを食べた際に、まさにそのことを感じたのだ。パテもリエットもペースト状に組織を潰すが、こうした組織をどのように活かすのかというのが「シャルキュトリ」の一つの技術なのではないかと実感したのだ。そしてそれを種類ごと、部位ごとに適切に加工をしていく技術が卓越しているように感じられた。
日頃から食材と向き合うシェフからすると当たり前のことかも知れないが、食べ手がそれを感じられるというのがゾザヤ氏の技術の高さを物語っているように思う。筆者も海外出張などで現地のシャルキュトリを食べることも多かったが、ここまではっきりと意識させられることはなかったため、慧眼した思いのする体験であった。
【3つの顔】
続いて提供された「ヴォライユ3種のパテ・アン・クルート リンゴとビーツのジェル バスク風シードル」はゾザヤ氏の哲学が見え隠れするような一品であった。鶏、雉、鴨を用いたパテ・アン・クルートだが、それぞれの味がしっかりと感じられ、程よい塩味に滑らかさと柔らかさ、肉感のあるテクスチャーにサクッと香ばしくアクセントを加えるパイがとても印象的だ。パイも内側はしっとりしているが、その側はクリスプ感がありそのコントラストもパイの良さを感じさせてくれる。

ビーツはほのかな大地を想わせる香りがして、味わいにも厚みやコクを感じさせてくれている。リンゴはその爽やかで軽快な香りが印象的に香り、レッドオニオンはシャキシャキとした触感と甘み、そして添えられた菜がグラッシーな印象を出してくれている。添えられている薬味が大地や草、果実といった自然を感じさせてくれる。
食べていて、ふとカルバドスの生産者から見せてもらった風景が蘇った。とても自然が豊かで、動物との距離も近く長閑な場所だし、イノシシも出てきて食べるという話を思い出した。風が下草を撫でてほのかに土のにおいを運び、風が吹く先には野鳥やリンゴの木が見える。そんな情景が食べていて浮かんできた。バスクは行ったことがないので、同じりんごの産地であるカルバドスが浮かんだのかも知れない。

このパテ・アン・クルートからは、ファルスの塩加減が日本とは異なることに加えて、パイをつくるパティシエ的な面、肉の専門家としての面、そして総合的な作品を仕上げるシェフとしての面がそれぞれ感じられた。
特に塩加減を含め、素材というよりも全体的に向こうで(フランスで)食べた味というのを思い出させてくれた。自然と食材の調和という一枚の絵に近いストーリーを想起させてくれるような一皿であり、思わず感動で久々に涙腺が潤んだ。
【家庭が見え、文化を感じた】
続いて提供された「豚の頭のスナッケ」は、郷土を感じさせてくれるような一皿だった。添えられたピペラードソースは、トマトの熟れた甘さがとてもよく感じられ、赤唐辛子はハンガリーのパプリカにも似たコクを演出しており、野菜の甘さと旨味が凝縮されていた。売れたトマトが凝縮されたソースはラタトゥイユに似た味わいで、南仏らしさを物語っているように感じた。ゾザヤ氏にとってもこうした味わいが故郷の味わいなのではないかと思わせてくれる。

蛸も丁寧に柔らかく煮込まれており、豚の頭のスナッケは外側のカリッとした触感に柔らかな脂身とのコントラストが印象的だ。柑橘にも似た清涼感がわずかに感じられ、脂の重さを緩和してくれている。

そして秀逸なのが、ピペラードとは別に添えられた赤ワインソースだ。一口でその丁寧さが感じられ、コクや甘味、酸味といった味わいのバランスだけでなく、全体として奥行きを感じさせながらアコーディオンのように香りが伸びることで、様々な素材が使われていることを感じさせてくれている。
続く「パリジェンヌ風ブーダンノワール」と「豚肉のパイ包み」も、ヨーロッパに根付く食文化を強く感じさせてくれる品であった。
20年近く前東欧を旅行している際、豚の屠殺をして加工するお祭りに行かないかと声をかけてもらったことがある。小さな村で風習が残っていることに驚いたのだが、ゾザヤ氏の「ブーダンノワール」や「パイ包み」は、そうした文化やお祭りという伝統を想起させてくれた。長い歴史の中、シャルキュトリが時に祝祭のごちそうであり、時に生活という家庭の場において身近な存在であるということを理解させてくれたように思う。
食文化が多様化している今日、昔のような「ごちそう」というものも変わってきている。ゾザヤ氏が素晴らしいのは、そうしたクラシックで時折家庭が垣間見れるごちそうを、フランスの伝統ある食文化の作品として昇華させている点だと思った。組織という視点、ファルスと外側(パイ)、食文化における食肉加工、自然と食材、たった五品だが様々なことを教えてくれた気がした。




【古酒の経験をどのように伝えるか】

ゾザヤ氏の料理ばかり触れていたが、ペアリングとして出されたワインも忘れてはならない。特に今回は貴重な熟成酒も多かったが、肉=赤という先入観ではなく、白ワインが多く合されていた点も見逃せない。
肉=赤という図式では、赤ワインの持つタンニンや赤系フルーツの香りが淡白ながら繊細の素材の持つ香りや味わいをマスクしてしまうこともある。今回はローヌのみでのペアリングであったが、例えばギリシャのダフニのような爽快感のあるワインやリオハの熟成したロゼなどとも合わせてみたいと感じた。
終盤に差し掛かり、Ermitage Blanc Le Meal 2009を頂いた時に、ワインそのものとは別に熟成酒における一つの懸念を感じた。それは、こうした卓越した古酒を日本で将来販売することが難しくなるのではないだろうかということだ。
理由は大きく2つあるが、1つはこれから育ってほしい層が熟成酒を飲む機会が限られていること、もう1つは、それに伴い熟成酒の良さが判断できなくなってしまう可能性があることだ。特に後者は、フレッシュなワインやナチュールに慣れ親しんだ方からすると、異質に感じられることもあるだろう。
クラシックな産地ほど産地のスタイルが味わいに反映されるが、そのスタイルを飲みなれていない方々にとっては、良さ以前にとっつきにくさというものが生まれてきていると感じる。昔に比べて、シャプティエのような地区を代表する卓越した生産者の古酒を飲める機会も少なくなってきている。飲み手に感動を与えるワインは代えがたい経験になるが、その経験をいかに次世代に繋げて行くかということを考えなければならないと感じた。
【技術+社会関係資本】
ゾザヤ氏の料理、そしてシャプティエ氏のワインと夢のような共演の時間はあっという間に過ぎていった。一夜限りの二人のコラボレーションを実現させた、ザ・リッツ・カールトン東京総料理長サンドロ・ガンバ氏の存在も大きい。改めて、ホテルならではのイベントであったと感じたし、こうした機会が日本で得られるのも大変喜ばしいことだと思う。
プロとしての専門性の高さだけでなく、社会関係資本の豊かさがこうしたイベントを創り出していく。今の時代、技術だけでなく、様々なネットワークの構築も必要になってくる。人材不足が懸念される業界だからこそ、こうした差が企業の価値創造の差として表れてくるというのを如実に感じたイベントであった。素晴らしい機会にお声がけを頂けたことに感謝し、ザ・リッツ・カールトン東京の次なる驚きに期待していきたい。
【参考文献】
Jean-Pierre Poulain & Edmond Neirinck『Histoire de la cuisine et des cuisiniers』(ジャン=ピエール・プーラン, エドモン・ネランク(2017)『フランス料理の歴史』(山内秀文訳)角川ソフィア文庫)
澤野 祥子, 水野谷 航, 食肉の肉質を決める筋線維タイプの重要性, 化学と生物, 2019, 57 巻, 11 号, p. 663-664