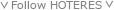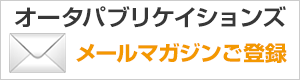一杯のお酒には、浮かび上がる風景や情景がある。記憶の中にあるもの、はたまたそうではないもの。グラスに浮かぶ憧憬はどこから生まれるのだろうか。シリーズ「味わいの原風景を探して」では、心に浮かぶ味わいが生まれる景色をお伝えしていきます。第一回は、ニッカウヰスキー 余市蒸溜所です。
【余市に降り立つ】
「余市のモルトには潮の香りがする」。よく言われる表現であり、自身の記憶を辿ると感じた覚えがある。しかし、それよりも燻したような香りと甘いニュアンスが印象的だった記憶が、朧気ながら浮かんでくる。あの味はどこから来ていたのであろうか。

仁木から余市に向かい、改札で支払いを済ませて駅を降りると、どこからか香ばしいにおいが流れてくる。周りに目をやると、ウイスキーの樽が駅出口左手に飾られており、樽からの香りかと思い近づいてみたが気のせいであった。駅正面から蒸溜所の正門が見える。
正門の横に掲げられている表札には「黒川町7丁目6番地」が記されており、駐車場からは「NIKKA WHISKY YOICHI DISTILLERY since 1934」のサインが見える。駐車場の整理をされている方から、余市蒸溜所と記載があるのはここだけで、穴場だと教えてもらった。


竹鶴氏と余市蒸溜所に関する記事や本は多くあるが、関連書の中で余市や黒川町という土地がどのような土地であったか、ということに触れられている書物は少ないように思う。数ある候補地の中から余市が「ためらうことなく」選ばれたとするならば、その地の歴史や産業の変遷を知ることも重要であると思う。地層を確認するように、自然と歴史が堆積するテリトーリオに目を向け、風土の成り立ちを知ることで、それが育む味わいの一端を知ることができるようになるのではないだろうか。
【余市という地】
余市は、ニシン漁業の栄枯盛衰、農場制成立による活性化、金属鉱山の再開と閉山を経験している。中でも、蒸溜所選定の際の鍵となったりんごを中心とする果樹農業の発展があり、今ではりんごだけでなく、近隣の仁木町と併せてワインツーリズムも積極的に行われている。
『余市町の社会・経済構造分析』によれば、余市への定住は江戸時代の松前藩の成立と場所請負制度に始まる。1688年神威岬以北への婦女子航行禁止により定住は遅れたが、この時期にはアイヌの人々が居住し、余市町の基礎作りを担っていた。移住が増えたのは1869年(明治2年)に場所請負制度が廃止されてからであり、戊辰戦争に敗れた会津藩士の一部が小樽へ送られ、その後、余市川流域の山田、黒川地区に移住をした。1890年~1900頃には、香川県や徳島県からの小作移民の募集や、空知から越前・越中の団体が移住し、黒川牧草地での水田耕作、稲作も行われるようになった。駅前にある「かくと徳島屋」は、その名残を感じさせてくれる。
『余市農業発達史』を読むと、その入植により産業がどのように変化してきたのかも見えてくる。同書によれば、北海道での果樹栽培は、函館付近の七重村(現七飯町)にプロシア人(現ドイツ)のガルトネルが、1869年(明治2年)に開墾したのが始まりだと言われている。実際に道内に影響を与えたのは開拓使であり、明治政府の殖産興業政策の一つとして行われた。余市でも、黎明期は旧会津藩士が明治4年から5年に植樹を始め、1875年(明治8年)に黒川村農会社でも開拓使庁からの交付を受け開始、翌年に500本の苗木が下付されたため、各農家に数本づつ配布して試植を行った。
山田、黒川の両村農民の多くは旧会津藩士であり、りんご栽培の経験はなく苦労をしたそうだ。この様子は竹鶴氏の『ウイスキーと私』の中でも語られている。1879年(明治12年)に初めて結実、翌1880年には札幌で開かれた農業博覧会で参考品として出品したりんごが名声を博して、小樽方面に高値で取引されるようになる。この時の結実は、緋の衣と国光の二種であったそうだ。こうしてりんご栽培が広がっていった。

余市橋からの眺め(蒸溜所のある左手が黒川町、右手が山田町)
こうして大まかな流れを見ると、余市という地は北海道開拓史の中でも特徴的な形成がされて来たことが薄っすらと見えてくる。加えて、余市川による影響も色濃く出ており、古くはアイヌコタンがあったり、ニシン漁が盛んであったり、溢水による肥沃な泥炭地ができていたりなど、自然とその地に暮らす人々の歩み寄りが見える土地である。
そこに、ウイスキー造りに必要な条件(水、気候、ピートなどの原料)、よく知られた熟成期間のキャッシュフローのためのジュース造り、他にも鉄道や船といった運搬に関わることや土地代やご縁(地元の方との繋がり)など様々な要因が重なり、余市という地に蒸溜所ができることとなったのだろう。ニッカの名は「日果」、大日本果汁から来ており、昔の写真を見るとりんごの山からカルバドスの生産者のようにも見えてしまう。旧会津藩士の苦労が無くては、この地に蒸溜所が生まれなかったかも知れない。

一号貯蔵庫
こうした開拓史の想わせる情景は蒸溜所内にも残っている。熟成させる原酒は貴重な資産であり、火災といったリスクを避ける必要がある。竹鶴氏が蒸溜所設立の際に取ったのは、貯蔵庫を沼地に浮かぶ小島に建てるという方法だ。今、その一号貯蔵庫の周りは陸地になっているが、貯蔵庫の奥側には、通称「ニッカ沼」と呼ばれる沼地が現存している。

その一号貯蔵庫を含む十棟が、2022年から国の重要文化財に指定されている。ニッカウヰスキーは来年2024年で創業90周年を迎える。100年近くも前に、余市という地で今に残る蒸溜所が建てられたその苦労と情熱を想いながら門をくぐった。
【余市の香り】
蒸溜所の正門をくぐると、右手には発芽を止めるためのキルン塔が見える。現在は使用されていないが、スコットランドの蒸溜所を想わせる特徴的な建物にはピートの実物が飾られていた。炉にくべると独特の香りが生じ、それがモルトへと移るのだが、炉にくべる前の乾燥した状態ではその香りは感じられない。「余市のモルトには潮の香りがする」と言われるが、訪れた際の風向きもあるのか、海からほど近い(余市湾まで約800m)とはいえその影響は感じられなかった。それよりも、澄んだ印象のある空気感であった。


キルン塔の隣にある糖化棟と醗酵棟へと足を運ぶと、突如、シリアル感と共にバナナやトロピカルフルーツを想わせるエステルの香りが芳しく、辺り一面に感じられ思わず足を止めた。華やかさのある香りに少し驚いたが、蒸溜だけでなく醗酵においても長年蓄積したノウハウが活かされていることが感じられた。
醗酵はアルコール生成の過程としてだけでなく、コンジナーと呼ばれる香気成分を生む過程としても重要である。酵母の種類や温度、更に言えば、醗酵槽の種類やウォートの清澄度などが関係し、エステルを含む多様な香気成分が生み出される。先程感じたエステルが多いであろうウォッシュが蒸溜されて、どのような原酒になるのか。エステルの香りに思いを馳せずにはいられなかった。
そんな華やかで甘い香りを背に、向かい側にある蒸溜棟に向かった。扉をくぐると、蒸溜器の稼働する音に石炭を掬う音、熱気、そして先程とは裏腹に、モルティな香りに包まれた。ストレート型でヘッドの上部にしめ縄が飾られた印象的なスチルは、世界各国のウイスキー好きにとって憧れの風景の一つとなっている。先程のエステルの香りと蒸溜棟に漂うモルティな香り。原酒の多彩さをここでも感じることができる。
余市蒸溜所の蒸溜器の特徴と言えば、どっしりとしたスピリッツを生み出すための形もそうだが、なんといっても、石炭の直火で熱を加えているところにある。竹鶴氏が炉から蒸溜器の底までの距離を測りに再度スコットランドを訪れた逸話を思い出しながら、煌々と燃ゆる石炭の明かりに目を向ける。釜の底は1000度から1200度にものぼり、直火ならではの香ばしさが生じるようになる。温度の調整も炉の窓の開放時間を含め調整している。



温度のモニタリングはされているが、調整は手動という「格闘」が品質へのこだわりを感じさせてくれる
いかにも昔ながらの雰囲気を感じさせてくれる蒸溜器だが、モニタリングなど近代的な技術により蒸溜の具合を見極めている。ウイスキー造りには多くのエネルギーを要するため、近年の社会的潮流から新設の蒸溜所は様々な工夫がなされたりしている。余市蒸溜所でも、二酸化炭素排出量が少ない石炭など色々と開発が進められているそうだ。
合理化が進む中、ある種の魔術的な要素というのは他にはないUSPにもなりうる。石炭の直火という手間がかかるが、一種の制御しきれないファジーな要素を残すことで、余市の原酒には人の手によって造られるといういきいきとした印象が生まれているように感じる。

奥に見えるのが41号棟貯蔵庫
熟成庫があるエリアは元々沼地であったことに触れたが、今は陸地になっている。蒸溜棟や醗酵棟を背にして旧事務所を抜けると徐々に木や土の香りといった自然を想わせる香りが広がる。奥には41号棟の貯蔵庫(従来のダンネージ式とは違い、自動式で貯蔵)が見える。キャパシティがある分、上段と下段で熟成環境が異なるため管理も複雑になる。

蒸溜所内には、移設された竹鶴氏の邸宅がある。邸宅の中には、実際に氏が使用されていたものが数多く展示されている。様々なジャンルの本があったが、竹鶴氏らしい学術書も多く見られたのが印象的であった。理論に裏打ちされた品質、飽くなき探求というのが竹鶴氏の生活の中からも感じることができる。
【余市の味わい】
貯蔵庫の前にはニッカミュージアムがあり、様々なニッカの歴史に関する史物が展示され、奥にはテイスティングができるコーナーも併設されている。ミュージアムから少し行くと、レストランとショップが併設されている。今年の4月よりレストランは改修され『RITA’s KITCHEN(リタズキッチン)』として営業をしている。竹鶴氏の愛妻リタさんが残したスコットランドや日本でのレシピメニューの再現もされている。



NAS以外のジャパニーズモルトの入手が困難になってから久しいが、余市蒸溜所では3種類のキーモルトというものが蒸溜所限定で販売がされている。自身が昔飲んで感じた余市のイメージは、燻したような香りと潮っぽさ、樽やドライフツールの甘さ、メローでありながらボールドな味わいと、個性とバランスに優れたものであった。蒸溜所を一巡りした後、3種のキーモルトを味わってみた。

『ピーティ&ソルティ』
色合いはゴールド。ピートの香りの奥に、少し熟れたフルーツのニュアンスがある。ピート由来の仄かなヨードっぽさとクローブやクレゾールのような香りといった少しメディシナルな印象に革製品のような印象がある。僅かなシリアル感とストーンフルーツやコンフィチュールのような雰囲気がある。
味わいは辛口、アルコール感はやや高く、僅かにタンニンを感じる。口に含むとグラッシーなフレーバーの後に、香りよりも甘くフルーティーでほんのりとフローラルな印象が口に広がる。一瞬ソーピーなニュアンスを感じるが、ドライフラワーのような印象とモルト感が次第に出てくる。余韻に僅かにシリアル感を感じ、アルコールの暖かさとピートの風味が長く続く。
蒸溜所ではキルンの姿は見ることが出来なかったが、ピートの具合はバランスが良く中盤以降はスピリッツが持つ多彩な香りが口の中に広がる。蒸溜器で感じたモルティな印象とは異なり軽めのスピリッツであることから、醗酵と蒸溜の組み合わせがよく管理されていることが伺える。潮のニュアンスはグラスからは思いのほか感じられない。

『ウッディ&バニラ』
色合いはディープゴールド。はっきりとした木材の香りやバニラ、シロップといった甘い印象がある。やや高めのアルコール感、ほのかに木工用ボンドのようなエステリーさ、木酢のような酸味に紅茶のジャムを想わせる印象もある。そのせいか、アップルブランデーのようなニュアンスも感じられる。
味わいは辛口、アルコール感は高く、口当たりはまろやかだが僅かにタンニンを感じる。香りよりも中盤以降エステルの印象が強く出ており、次第にフローラルな印象へと変化していく。香りには感じなかったスパイスの雰囲気がある。アルコール感と相まって甘い印象とは裏腹にドライな印象があり、余韻に僅かにインセンス様の風味とシリアル感、リンゴを食べた後のような風味を感じる。
今回は見ることができなかったが、余市蒸溜所にはクーパーを担当する部門がある。このキーモルトは名前にある通り、樽からの影響が色濃く出ている。特にスパイス感やお香のような香りは他のキーモルトよりも特徴的に感じられる。オーク由来のラクトンを含むエステルなのか、醗酵由来のものなのかは分からないが、有機酸やエステルの雰囲気が良く感じられる。原酒の多彩さを支える樽の技術が感じられる。

『シェリー&スイート』
色合いは僅かにカッパーがかったディープゴールド。モルト感、丸い印象がある。黒蜜の濃く甘い香りの奥に、醤油や味噌などの醗酵系に似た香り、レーズン、普洱茶やキノコ、ベチパーのようにほんのりとアーシネスを想わせるニュアンスもある。香りからも重さと濃さを連想させる雰囲気がある。
味わいは辛口、アルコール感は高く、タンニンも僅かに感じる。香りの印象に、アグリコールのホワイトラムにも似た、少し焦がしたような砂糖やアップルパイのような雰囲気を感じる。中盤以降に顔を出すモルト感とフルーツ感、フローラル感のバランスがよく、余韻には香りにあるような甘さとともに、原料自体の穀物的な甘さが一体となって広がる。やや乳酸っぽい雰囲気も感じられる。
このキーモルトは蒸溜器で感じた香りが色濃く反映されている。僅かに感じる焦がしたような雰囲気は、直火からの影響かもしれない。他のキーモルトよりもモルティな印象と重い印象がある。醗酵だけでなく蒸溜速度やカットポイントも異なるのかもしれない。色と香りにはシェリーらしさを感じられるが、それ以上にスピリッツの骨太さと原料由来の香ばしさと旨味を感じることができる。竹鶴氏の著書の中でもグレーンよりもモルトは重いという表現をされていたが、そのことを感じられる味わいだと思う。
【創業者の想い】
こうして3つのキーモルトを味わってみると、原酒の多様さの奥に蒸溜所内で感じた香りと竹鶴氏の想いを探すことができる。『ピーティ&ソルティ』からは本物志向でピートが入手できる地として選ばれたことが、『ウッディ&バニラ』からはウイスキーには熟成(樽と自然の影響)が必要なことが、そして『シェリー&スイート』からは特徴的な蒸溜器が生み出す味わいが感じられるように思う。どのキーモルトにも、奥底に流れる竹鶴氏の情熱があるように感じる。
自身が昔余市のモルトに対して持っていた潮のニュアンスは、今回の訪問では感じることができなかった。海沿いで熟成されるスピリッツ(もしくは海沿いの原料をそのまま使用するようなスピリッツ)には、どことなく潮っぽさを感じさせる印象が出てくる。季節や風向き、潮の満ち引きなど様々な理由があるかもしれない。
訪れた季節は二十四節気で言えば大暑にあたる時期であったが、初夏のドイツ北部を想わせる天候であった。広田らの報告(広田 他, 2017)にもあるように、昔と比べて熟成環境にも変化が出てきていると思う。今回は夏だったが、雪深い冬の澄んだ空気の中では蒸溜所で感じる香りも違うことだろう。
時代と共に近代的な技術や環境の変化というものはある。市場の需給やトレンド、マーケティング的な側面もある。事業として考えた際、そうした変化に対応するすべを持つというのは必要である。しかし、そうした中でも創業の想いというものは根底にあり、製造業であれば製品や技術に反映されていなくてはならないと思う。余市蒸溜所にはそれが感じられた。飲むだけは分からなかった竹鶴氏の想いが、今回の訪問を通じてウイスキーから汲めるようになった気がする。
移ろいゆく季節によって、その風景も香りも変化する。願わくば、次は雪深い季節に訪れてみたい。
【訂正】2023/08/18 15:00
試飲コメントの商品名に誤りがあり、訂正致しました。
読者の皆様ならびに関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
【参考文献】
竹鶴政孝(2014)『ウイスキーと私(電子書籍版)』NHK出版
ダイヤモンド社 編『ヒゲと勲章 ニッカウヰスキー社長 竹鶴政孝 「ウイスキー革命は俺がやる」 歴史をつくる人々』
木村純子・陣内秀信(2022)『イタリアのテリトーリオ戦略: 甦る都市と農村の交流』白桃書房
余市町 編(1983)『余市町の社会・経済構造分析』大明堂
余市教育研究所 編(1968)『余市農業発達史』
広田 知良, 山﨑 太地, 安井 美裕, 古川 準三, 丹羽 勝久, 根本 学, 濱嵜 孝弘, 下田 星児, 菅野 洋光, 西尾 善太, 気候変動による北海道におけるワイン産地の確立, 生物と気象, 2017, 17 巻, p. 34-45
担当:小川