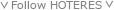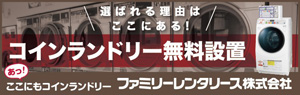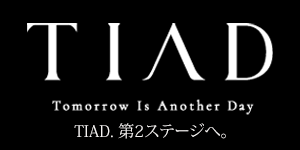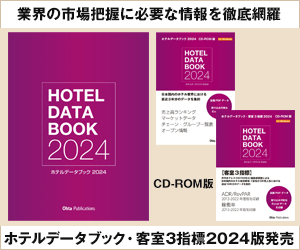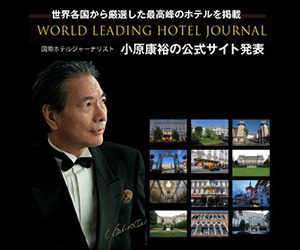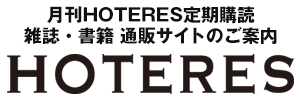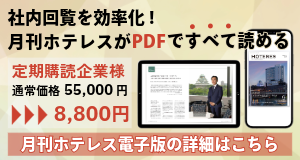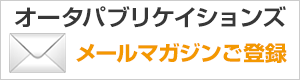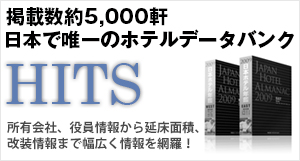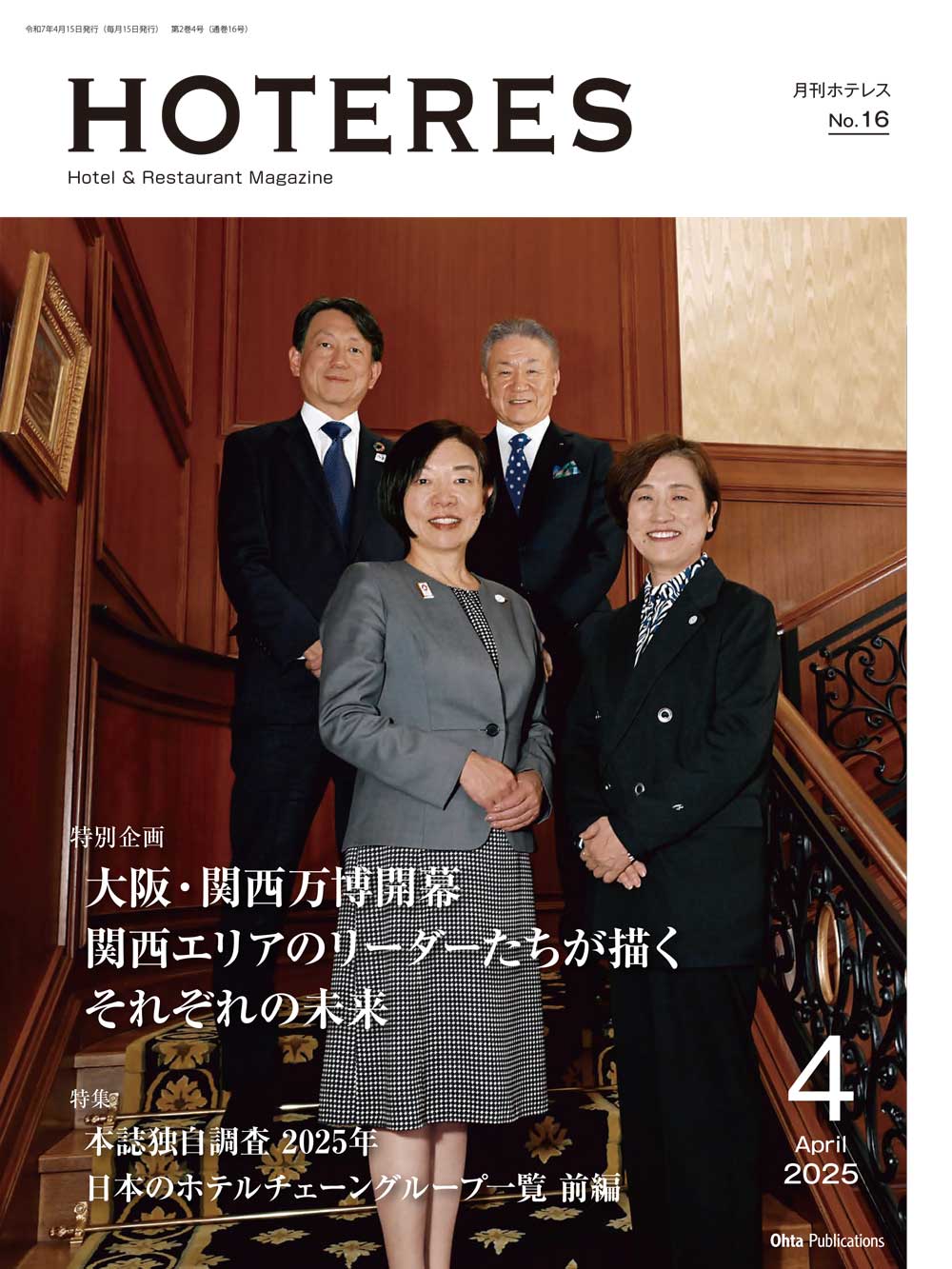観光立国・日本を考える際、施設として検討すべき内容の一つとして考えられる喫煙環境。そこで日本の喫煙環境の今と、これからの在り方について、海外と日本の環境の実態と、訪日外国人観光客の生の声をもとに考察する。
2014年、来日した外国人観光客の数は1340万人を超えた。国の指針としては今後、訪日外国人3000万人を目指しているのが現状だ。中でも前年比83%の増加率を見た中国人観光客などは、歩行者天国となる休日はもちろんのこと、平日も銀座の中央通りに何台もの観光バスが並び、休日に引けを取らない賑わいを見せているほどだ。とにもかくにも昨今のインバウンドによる観光客の増加には目を見張るものがある。それに加え、2020年の東京オリンピック開催に向け、Wi-Fi環境の整備、案内標識の多言語化、東京観光ボランティア「おもてなし東京」の始動など、日々グローバル対応の強化に向けて一斉に動き出している。 その流れの中で宿泊、飲食施設に於ける喫煙・分煙・禁煙の判断については一部の地域を除き、行政の規制ではなく、各々の施設の事業者もしくは施設管理者により、それぞれの実情に合わせて選択されているという状況である。
日本の喫煙環境は、グローバル化に合わせて変化していくのか?喫煙環境について、国際比較や訪日外国人へのアンケート結果など、いくつかの側面から考察してみた。

まず来年に控えるリオデジャネイロ及びソチ、ロンドン、バンクーバー、北京の過去4大会が開催された都市と東京との喫煙環境の比較だ。(表①)を参照して貰うと解るように飲食施設の屋内に於いては、「禁煙」となっている都市と「喫煙可」となっている都市とがあり、東京のみ「分煙」という環境が存在する。一方、路上など屋外に於いては、指定場所以外禁煙という屋外の「分煙」を導入している東京を除き、基本、いづれの都市も屋外は喫煙可となっていた。
オリンピック会場及び選手村などに於ける喫煙環境をどのように整備するかについては、(表2)見ると、東京だけでなくリオデジャネイロも未発表だが、ソチより過去の大会に於いては屋内は禁煙、敷地内の屋外では指定場所でのみ喫煙可能というスタイルが取られているようだ。
このように、国際的に見た際に東京の喫煙環境の整備は屋内・屋外それぞれにおいて、非常に細やかになされていることが解る。
また現在、日本に於いては飲食店の67%、オフィスの97%が禁煙もしくは分煙の環境を整えており、諸外国とは異なる、「分煙」という選択が存在しその環境整備を進めている日本は、世界に類似する例がまだ少ない、独自のスタイルが進んでいる国だともいえる。因みに昨年末から今年の頭にかけて、JTBグローバルマーケティング&トラベルと週刊ホテルレストランが共同で実施した、訪日外国人観光客へのアンケートで、日本の「分煙」という考えに基づいた、屋内・外の喫煙環境についての感想を聞いたところ、喫煙者・非喫煙者共にほとんどの回答が「抵抗感がない」という結果になっており、非喫煙者に限った回答結果でも「抵抗感を感じる」との回答は約1割に留まり、スムーズに受け入れられていた。

また、同アンケートでは、日本の喫煙環境が諸外国の環境整備に比べ決して劣っていない、むしろ優れているという評価を得ていることが解る結果も得られていた。(自国と日本の喫煙環境の比較に於いては64%の訪日外国人観光客が「日本の方が良い」と答えている。喫煙者と非喫煙者に分けて回答率を見た場合、喫煙者からは80%、非喫煙者からも61%の高評価を得ている。更に日本の現行の喫煙環境ルールでの再訪日意向に対し全体で約80%が「イエス」と回答。非喫煙者のみのデータでもほぼ同様の意向を得ていることからも、全面的な禁煙化が強く求められているわけではないことが解る。)むしろ要望が高いのは喫煙スペースの設置及び喫煙可否に関するサインの提示であったり、飲食店や宿泊施設の「喫煙ルール」の案内や設置についてであった。※【資料】訪日外国人調査を参照
このことから今後、ホテルや飲食店に於いて求められる喫煙環境として最適なのは、誘導のためのサインなども含め、更に分煙環境を進めることであることが見えてくる。例えばホテルの共有部においては、理想としては屋内に喫煙スペースを設置することだが、スペースなどの問題でそれが難しい場合にも、少なくとも屋外での環境整備を検討したい。その場合には、利便性や動線、造作など喫煙者のみならず、非喫煙者にも配慮がなされたスペースとするべきである。

本年も観光世界一都市に京都が選ばれるなど、東京のみならず日本は世界の観光産業、旅行者からの注目が高い国であることは疑いの余地がない。その点から見ても東京オリンピック誘致の際に強く世界にアピールした「日本のおもてなし」を、分煙に於いても外国人観光客に感じて貰え、喫煙者にも非喫煙者にも心地よく日本での時間を過ごして貰えるように、観光に携わるすべての産業が今後も分煙環境整備に取り組んでいくことが望まれる。