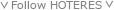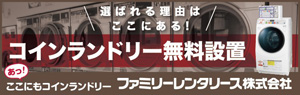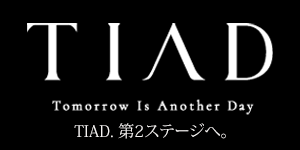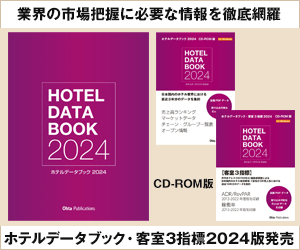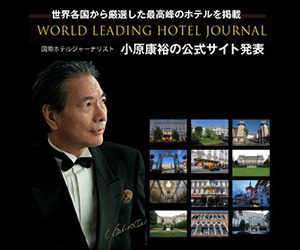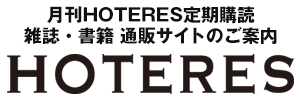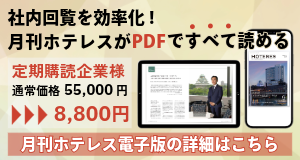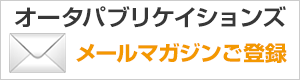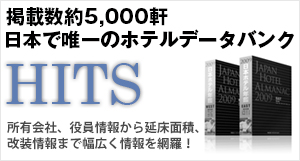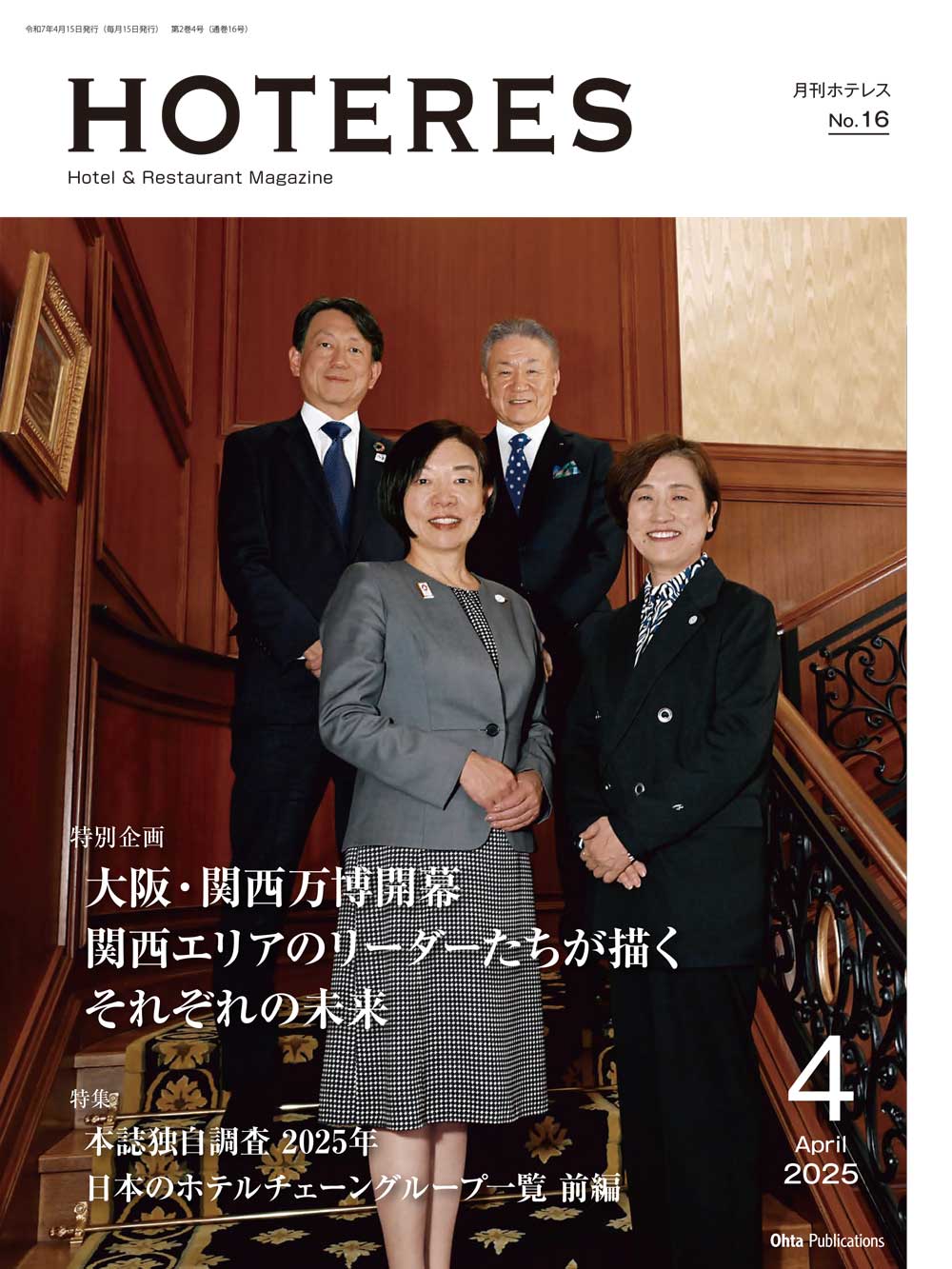お茶の水に立地する山の上ホテルは、小さなホテルである。ここはもともと、教会建築、学校建築を多数手がけた、ウィリアム・M・ヴォーリズが設計し、「佐藤新興生活館」という生活改善を目的に西洋の様式などを女性に啓蒙するための施設として建てられた。戦後、GHQの接収を経て、1954 年に創業者の吉田俊男がホテルとして開業させたという逸話がある。長い歴史の中では、多くの作家が「カンヅメ」となり、名作が誕生する舞台ともなってきたことは有名である。
このホテルは、規模こそ小さいが、料飲サービスにきわめて力を入れている。客室数35 室ながら、実は料飲サービス施設を7 軒も持っている。しかも、そのうちの2 軒はバーである。
バーとはとても不思議な場所である。カウンターに座ると、誰もが肩書きや社会的地位を忘れて、自分をじっくりと見つめることができる。その意味では、多くの著名人が投宿したこのホテルのバーが担ってきた役割は、きわめて大きいものであるといえよう。
今回は、ここで30 年近くカウンターを守ってきた大沼氏にスポットを当て、バーテンダーという仕事の一端を垣間見させていただいた。
なぜバーテンダーに
徳江 早いもので、われわれがここでお会いしてから四半世紀以上の月日が流れました。あの頃、信さん(注:大沼氏のこと。以下同様)はまだカウンターに入りたてで、私はまだ学生でしたね。
大沼 2 人とも若かったですね~(笑)私はこのホテルに勤めて30 年になります。
徳江 かつては終身雇用が当たり前のこの国でしたが、最近は転職をする人も増えました。まして、もともと転職する人が多いこの業界にあって珍しいですね。そんな信さんは、そもそもなぜ山の上ホテルに入社したのですか?
大沼 実はもともと、洋食の料理人をやりたいと思っていたんです。既に高校の先輩が山の上ホテルに就職をしていたことと、先生の勧めもあってこちらにご縁をいただきました。でも、料理人枠が一杯だったのと、創業者の吉田俊男が「和食向きの顔だから」と決めてくださったこともあり、まずは「てんぷら」のホール担当になったんです。
徳江 もともとは料理人を目指していたとは驚きです。
大沼 でも、バーがすぐ隣で、バーテンダーの先輩たちにかわいがってもらったこともあり、バーテンダーに転向することになりました。