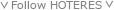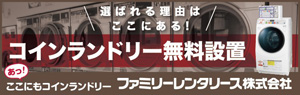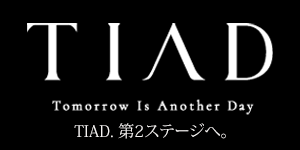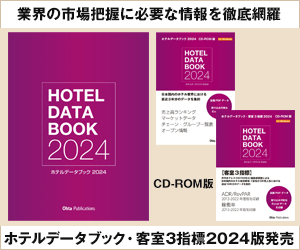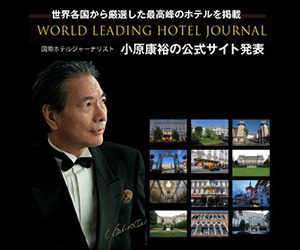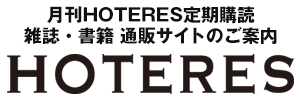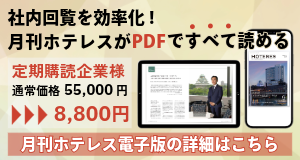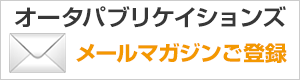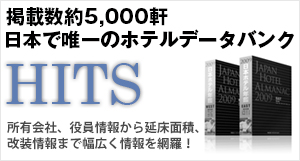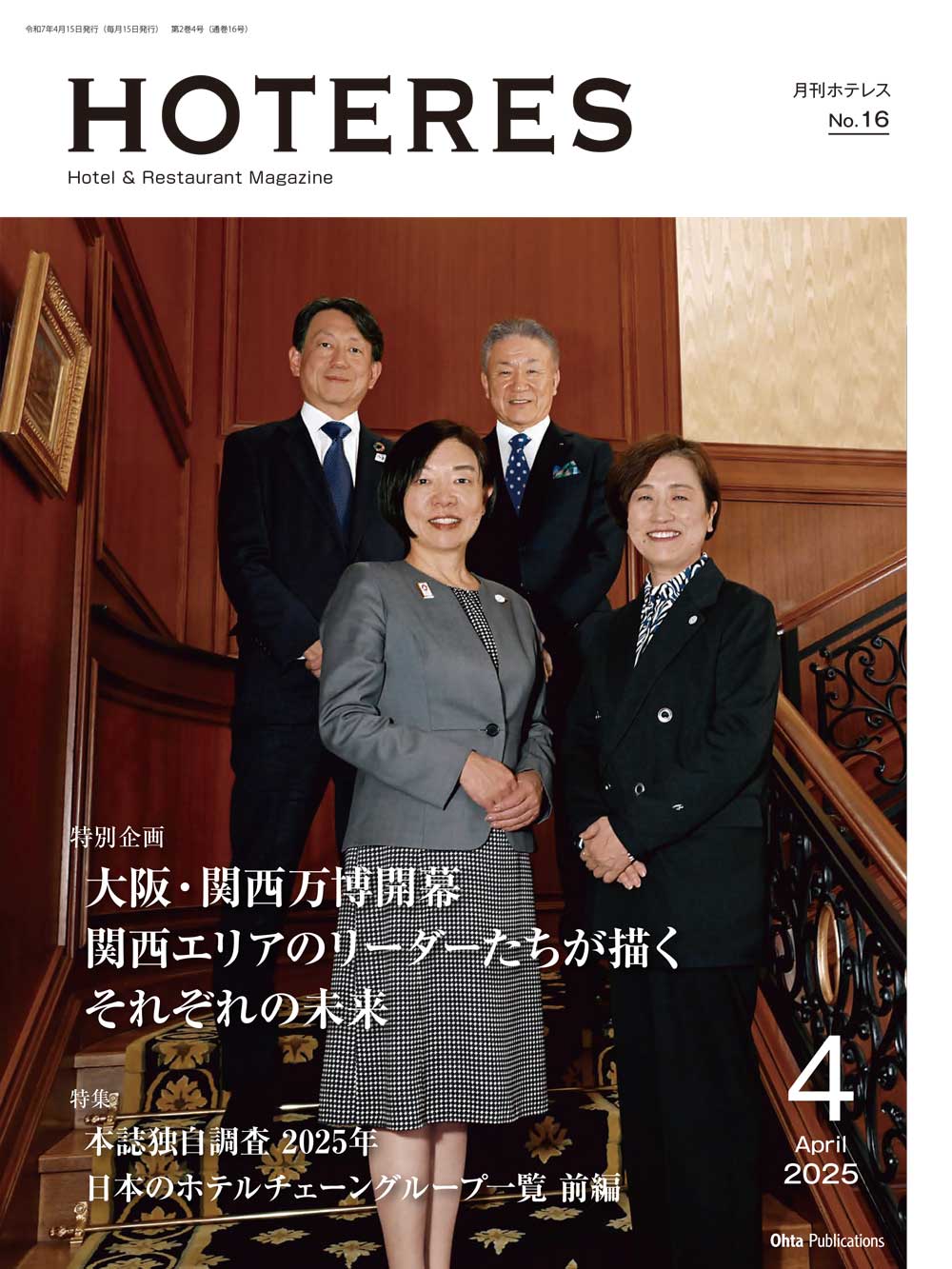日本代理店マックフーズ(☎ 03-5646-2941)展示場ブース前でキャビアの商品を説明するリリーさん
チョウザメには一尾ごとにIC チップ
チョウザメには1 尾ごとにID がついている。毎月1 回、1 尾ごとに成長具合、病気になっていないかなどを検査する。昔は番号札をヒレに張って管理していた。今はIC チップを埋め込んで管理している。商品の缶詰の後ろにはバーコードが張ってあり、これでどういう生育過程を経てきたキャビアか全部分かる。
リリーさんは「トレーサビリティーをしっかり導入しています。いつ生まれてどういうものを食べて、だれが管理してきたか。安全・安心の思想を盛り込んだやり方です」。最先端の技術を導入して安全・安心をしっかりアピール。
湖で育てた後、キャビアが取れそうに成長したら、チュウゾウという地名の別の場所に車で移し2 ~ 3 カ月育てる。採取する前にわざわざ場所を変えるのはエサのない場所でエサを与えず内部をきれいにするためと、臭みなどを取るためだ。
「チョウザメも精神的に安定します。精神的に不安定になるとキャビアの量も少なくなります。そのすぐ隣が加工工場になっており、その工場にもいつも冷たい水が流れ込んでおりキャビアを取り出すには最高の環境になっています」(リリーさん)。
アラン・デュカス氏も品質には納得
開腹後にキャビアを取り出し、洗浄、水切り(7 分)、検品、検量、塩添加、パッキングと続くがこれらの工程が15 分間という短さ。ストップウオッチを見ながらの作業が徹底されている。
こうした徹底的な品質管理が良質なキャビアを生み出し、2011 年からはルフトハンザ航空のファーストクラスに採用されている。キャビアメーカー37 社からブラインド・テストの結果により選ばれている。
さらに洗練されたフランス料理で定評のあるアラン・デュカス氏が千島湖を実際に訪問し品質に納得。世界中にある彼のレストランで採用されている。またパリにある星付きレストランでも同社のキャビアを採用している店が多い。さらにパリのキャビアの名店であるペトロシアンやキャビアハウスでも販売している。このように「中国産のキャビアはパリだけでなく世界の著名なレストランのみならずキャビア専門店でも取り扱われている」(リリーさん)。
キャビアが取れそうなチョウザメをいつ移動させるのか。それはチョウザメのおなかに細い管を刺して、2 ~ 3 粒取り出し、0.2㎜とか0.3㎜とかキャビアがどのくらい成長しているのかを実際見て決める。キャビアの取れる時期は9 月から翌年の1 月までとされている。
日本マーケットは魅力的
輸出先はドイツが最も多く年間12トン。次がスイス、フランス、アメリカでそれぞれ10トン。日本は2 ~3トンとまだ少ない。
それでも日本のマーケットは魅力的という。日本のキャビア輸入量は毎年13トン程度。しかも半分は本当のキャビアであとの半分はキャビアもどきという。もどきとはチョウザメの卵ではなくほかの魚の卵であったりするというのだ。
中国産キャビアは日本人にとってイメージがあまりよくない。そのため「ホテルなどへの広がりがなかなか進まない。しかし品質に関しては自信があり、試食してもらい、年間を通じて安定して納入できることが分かってもらえればこれから増えていくものと思います」(リリーさん)と自信を見せる。
そのためにも高級ホテルだけではなく、街場のレストランも含めてすそ野を広げていきたい意向だ。価格面などでも一般的なスーパーでも十分取り扱ってもらえるものと考えている。
前述したようにキャビアの養殖技術は中国の国家事業の一つで、日本でいう農林水産省の部門が研究している。会社のトップは中国の研究部門の人が出向のような形でかかわっている。国家事業としてのキャビア。中国産というだけで敬遠するのは考えが狭すぎる。筆者も試食してみたが濃厚でクリーミー。塩加減もちょうどよく、後を引くおいしさを感じた。また見た目にも粒がそろっており、品質は上等と感じた。実際大手ホテルの料理長なども品質の良さには太鼓判を押しているが取引となるとしり込みする現実がある。「お客さまに提供する時点で中国産となると断られる」(大手ホテル料理長)ケースもあり、ホテル側に問題があるわけではない。いいものはいい、という考えを大事にしてお客さまに相対する姿勢が今後の経営に求められているように思う。