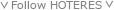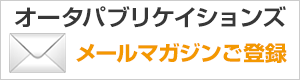前回まで、ホテルを取り巻く環境変化と、それに追随できていない日本のホテル企業の事業展開について述べてきた。最大の問題点は、「わが国のホスピタリティーは世界最高だ」という意識を持ちながら、特にラグジュアリー市場において、海外からの大々的な進出を許してしまったうえに、逆に海外への進出についてはごく一部にとどまっている点である。
では、わが国固有の宿泊業態と言える旅館においてはどうだろうか。日本が誇る「おもてなし」を、最も表現しやすい業態の一つが旅館であることは議論の余地がないだろう。しかし大変残念なことではあるが、旅館は 1990年代以降、軒数・客室数ともに長期低落傾向にある。
ご承知のとおり、旅館という業態が低落気味な主たる理由は、市場が団体客から個人客へとシフトしたことである。
高度経済成長とともに国内旅行者数も増加したが、その中でも大きな存在感を示していたのが社員旅行に代表される団体旅行である。多くの旅館は、1980年代ごろまでは急増する団体客需要に対応すべく高層化・大規模化に突き進み、「温泉ホテル」などとも呼ばれるようになったのである。しかしこの団体旅行が国内有名温泉地を席巻していたのは、バブル期のころまでであった。
その後、不況の長期化や郵政民営化などといった国の方向性の変化によって、こうした団体旅行そのものが激減した。また、好業績をあげた企業でも社員旅行は海外で、という流れもできつつある(※つまり、ここでも「海外に敗退」という状況が生じている)。
そのために、高層化・大規模化した旅館の多くが、旅行代理店経由を中心とした団体旅行の減少とともに苦境に陥ることになったのは当然のことと言える。
また、旅館という単体のみならず、温泉街という地域としてみた場合でも、かなり厳しい状況に陥っていることは周知の事実であろう。
ひところ、熱海のゴーストタウン化が報じられていたのは記憶に新しい。また、鬼怒川は温泉街まるごと倒産したような状況となってしまった。そして、別府も地盤沈下にあえいでいると伝えられた。こうした大温泉地の多くは、団体客の激減に直面しガラガラの施設を抱えたままどうすることもできなくなってしまっていったのである。
これも、旅館単体が厳しい状況に陥ったのと同じ理由である。すなわち、団体客から個人客へ、言い換えれば「市場環境の変化に対応できなかった」ということになる。
とはいっても、旅館がすべて、あるいは温泉街がすべてダメになってしまったわけではない。
例えば、松本に近い扉温泉「明神館」のように、現代の新しい設備を取り入れて快適な空間づくりに成功した施設もあれば、天草の「五足のくつ」や軽井沢をはじめとした各地の「星のや」のように、アジアのスモール・ラグジュアリー・リゾートに共通する空間づくりやサービスの提供を行ない、世界中から顧客を集める施設もある。
また、長野県の渋温泉や熊本県の黒川温泉のように、古き佳き日本の温泉街の風情を演出し、なかなか宿の予約が取れない温泉街も存在している。
つまり、旅館単体、温泉街という集合体のいずれにせよ、問題は対象とする市場セグメントがどう変化(例:団体客→個人客)し、その変化にどのように対応したかということに尽きる。
そして、変化に対応しきれなかった企業や地域が衰退している、それだけの話であり、この「地域」が日本全体という単位に広がるかもしれない、ということに注意が必要なのである。

東洋大学 国際地域学部国際観光学科 准教授- 徳江 順一郎 プロフィール